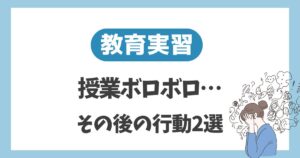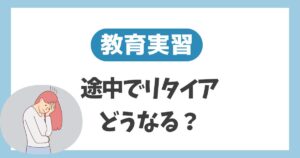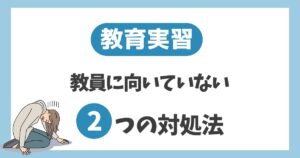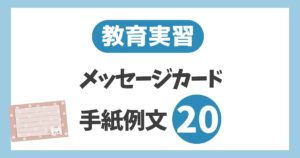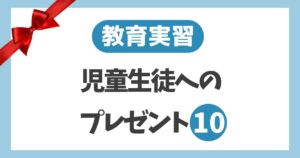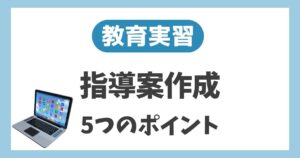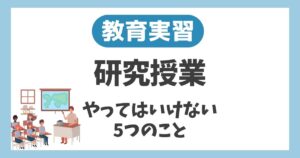【保存版】教育実習日誌の書き方|ネタ切れしない20の視点も紹介
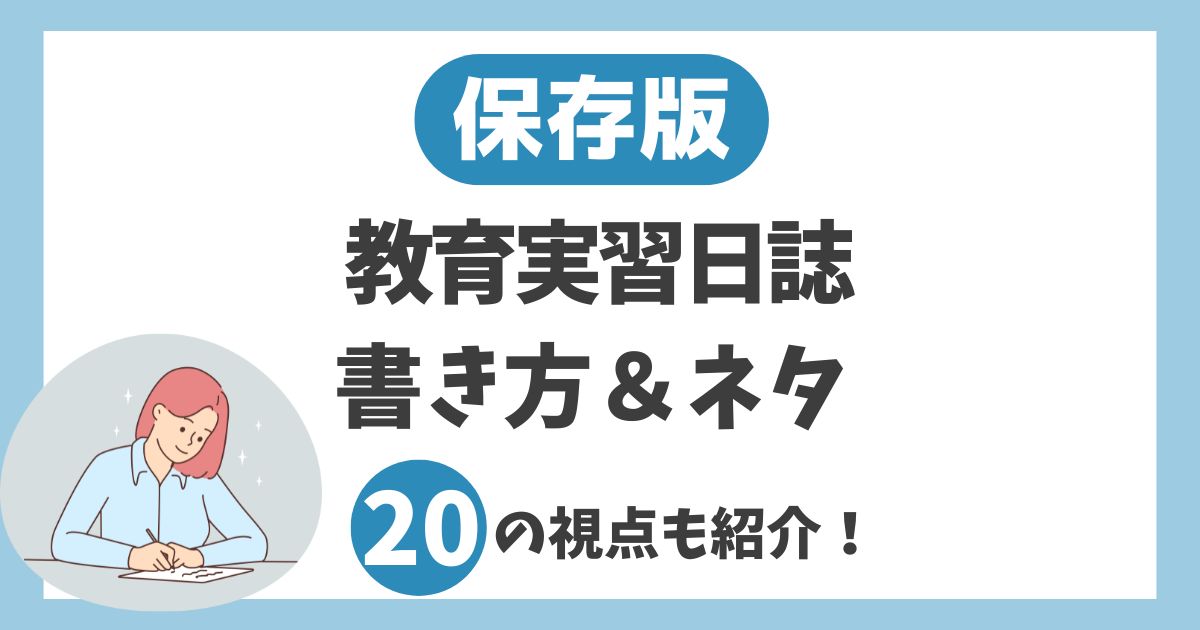
「教育実習日誌、どんなことを書けばいいんだろう?」
「毎日同じような内容になってしまいそうで不安…」
と悩んでいる教育実習生の方も多いのではないでしょうか。
教育実習では毎日、その日の学びや気づきを日誌に記録する必要があります。
何を書けばいいのか、どのように書けばいいのか、不安になりますよね。
実は、教育実習日誌には書くべきポイントがあり、それを押さえばスラスラと書けるようになるのです。
この記事では、教育実習日誌の基本的な書き方から、ネタ切れしないための20の視点、さらには具体的な文例まで詳しく解説します。
- 教育実習日誌の基本的な書き方
- ネタ切れしない20の観察ポイント
- 場面別の具体的な文例(初日・最終日の例文付き)
記事を読むことで、教育実習日誌をスラスラ書けるようになり、実習での学びをより深められるようになりますよ。
あわせて読みたい(タップで閉じる)
教育実習日誌の書き方

教育実習日誌は、単なる日々の記録ではありません。
実習での学びを深め、教師としての成長につなげるための重要な日誌です。
まずは、教育実習日誌の基本的な書き方について、解説していきます。
何のために書く?
そもそも、教育実習日誌は何のために書くのでしょうか。
教育実習日誌を書く目的は大きく2つあります。
- 自身の学びを振り返るため
→自身の学びを振り返ることで、翌日以降の実習に活かすことができる - 実習先の先生に学んだことを報告するため
→指導教員があなたの学びや成長・つまづきを確認し、適切なアドバイスができるようになる
つまり、教育実習日誌には「人に読んでもらう」という目的が含まれているので、自分だけが理解できる「メモ」ではダメ。
必ず、その日の学びの姿が人にも読んで伝わるように書く必要があるのです。
どんな内容を書く?
では、どのような内容を書けばよいのでしょうか。
教育実習日誌の内容は、「授業見学・観察の日」と「授業実践の日」で、若干書き方が異なります。
それぞれの日によって、以下ことを意識して書いていきましょう。
授業見学・観察の日
授業見学・観察の日は、以下の5つの項目を中心に記録します。
- 今日の目標
→その日に特に注目したい点や学びたいことを具体的に書きます - 実習・活動内容
→見学した授業の概要や、その他の活動内容を時系列で記録します - 気づき、学びになったこと
→指導教員の工夫や効果的だった指導方法などを記録します - 感想・考察
→観察した内容について、なぜ効果的だったのか、どのような意図があったのかを考察します - 取り入れたいこと・代替案・アクションプラン
→自分が授業を行うときに活用したい点を具体的に記録します
※実習日誌の形式によっては書き方が異なることがあります。ご自身の日誌の書き方も確認してくださいね。
具体的には、以下のようになります。
〈今日の目標〉
算数の授業における板書の工夫と、教師の発問の仕方を重点的に観察する
〈実習内容〉
1〜2時間目は5年1組の算数「合同な図形」の授業を見学しました。△△先生は、図形の性質を説明する際、実物投影機を活用して、実際に三角定規を重ねて見せながら授業を進められました。3〜4時間目は理科の授業を見学し、放課後は明日の授業準備と職員会議に参加しました。
〈気づき・感想〉
本日の算数の授業観察を通じて、特に印象的だったのは△△先生の板書と発問の工夫です。板書は左から右へ流れるように展開され、重要な用語は色チョークで強調されていました。また、「なぜ二つの図形が重なると思う?」「他の方法で確かめられないかな?」など、子どもたちの思考を促す発問が効果的でした。特に印象的だったのは、誤答があった際の対応です。「なるほど、そう考えたんだね」と一度受け止めてから、「では、実際に重ねて確かめてみよう」と、具体的な操作を通じて理解を深められるよう導いていました。この指導法により、児童が間違いを恐れずに発言できる雰囲気が作られていたと感じました。
〈取り入れたいこと〉
来週の私の算数の授業でも、△△先生のように具体物を使った説明を取り入れたいと思います。特に、図形の合同を教える際は、実物投影機を活用して、実際の操作を見せながら説明することで、視覚的な理解を促したいと考えています。また、発問については、「はい」「いいえ」で答えられる質問ではなく、「なぜ」「どうして」と理由を問う形式を意識的に取り入れていきたいです。誤答への対応についても、△△先生のように、まず受容してから、具体的な操作を通じて理解を深める方法を実践していきたいと思います。
授業実践の日
授業実践の日は、以下の5つの項目を中心に記録します。
- 今日の目標
→その日の授業で特に意識したい点を具体的に書きます - 実習・活動内容
→実施した授業の流れや、その他の活動内容を時系列で記録します - 上手くいったこと・上手くいかなかったこと
→授業での成功点と課題点を具体的に記録します - 感想・考察
→なぜ上手くいった/いかなかったのか、その要因を分析します - 自己反省・改善目標・アクションプラン
→次回の授業に向けた具体的な改善点を記録します
※実習日誌の形式によっては書き方が異なることがあります。ご自身の日誌の書き方も確認してくださいね。
具体的には、以下のようになります。
〈今日の目標〉
小数のわり算の導入で、具体的な場面を用いて児童の理解を深める。特に、既習の整数のわり算との違いを意識させる展開を工夫する。
〈実習・活動内容〉
5年2組で算数「小数÷整数」の導入授業を行いました。2mのリボンを3等分する問題を提示し、実際にリボンを見せながら立式につなげました。その後、グループワークで違う長さのリボンを等分する活動を行い、最後に学習のまとめをしました。
〈上手くいったこと・上手くいかなかったこと〉
【上手くいった点】
・実物を使った導入で、児童の興味を引き出せた
・既習事項との違いを明確にするため、整数の場合と比較する場面を設けた
【課題点】
・グループ活動の時間配分が適切でなく、まとめの時間が不足した
・机間指導の際、つまずいている児童への支援が不十分だった
〈感想・考察〉
実物を使用した導入は効果的でしたが、その後の展開で時間配分を誤ってしまいました。特に、グループ活動に予定より時間がかかり、重要な「まとめ」の時間が十分に取れませんでした。また、活動中に気づいた児童のつまずきに対して、適切なタイミングでの支援ができませんでした。
〈自己反省・改善目標〉
次回の授業では次の3つのことに気をつけて授業を組み立てていきたいです。
・活動時間を明確に区切り、タイマーを活用する
・机間指導の際、支援が必要な児童をチェックリストで管理する
・次回は板書計画をより詳細に立て、時間配分の目安を記載する
いつどのように書く?
教育実習日誌を書くタイミングには「コツ」があります。
効率よく時間が使うためにも、ポイントを抑えておきましょう。
前日のうちに「今日の目標」を書いておく
実習中の朝は、授業の準備や教材研究など、やるべきことが山積みです。
朝はその日の準備でバタバタするため、今日の目標を考える暇もなく、その日の実習が始まってしまうことも少なくありません。
(気づいたら、放課後に「今日の目標」を慌てて書く…なんてことも。。。)
そうなってしまったら、せっかくの成長のチャンスを逃してしまうことになってしまいます。
そこで、おすすめなのは「前日のうちに翌日のスケジュールを確認し、目標を書いておくこと」です。
前日のうちに目標を書いておけば、翌日の朝も落ち着いて実習に取り組むことができますよ。
こまめにメモしながら
教育実習は1日の出来事が非常に多く、すべてを覚えておくことは困難です。
そのため、実習日誌とは別にメモ帳を準備し、都度メモを残しておくことが大切です。
メモを残すときには、事実だけでなく、自分の考えたことも併せて書くようにしましょう。
「なぜそう思ったのか」
「どうすれば良かったのか」
といった考察も、その場で記録しておくことで、より深い振り返りが可能になります。
教育実習中のメモ術を身に着けておきたい方はこちらもチェックしておいてくださいね↓
できるだけ勤務時間内に
実習日誌は、できるだけ勤務時間内に提出しましょう。
放課後もスケジュールみっちりでなかなか書く時間がないこともあるかもしれません。
しかし、教育実習担当の先生はもっと時間がありません。
提出された実習日誌に、その日のうちにコメントを書いて返却してくださるため、勤務時間外に提出をしてしまうと迷惑をかけてしまうことになります。
空きコマや放課後のスキマ時間などを上手く活用して、勤務時間内提出を目標に書き上げるようにしましょう。
また、出来事や気づきが新鮮なうちに記録すれば、より具体的で深い振り返りが可能になるので、一石二鳥ですよ。
教育実習日誌でネタ切れしない20の視点

教育実習日誌を書く際、同じような内容の繰り返しになってしまう実習生は多いものです。
中には「書くネタが無い…!」と困り果ててしまう人も現れることでしょう。
そこで、「教育実習日誌でネタ切れしない20の視点」を紹介しますね。
以下の視点を意識することで、より深い観察と記録ができるようになりますよ。
授業見学のときの視点
授業見学では、漠然と眺めるだけでは、学び取れることが少ないです。
以下の視点から観察し、少しでも多くのことを学べるように努力してみましょう。
視点①:教師の発問について
発問の意図や効果、児童生徒の反応などを観察します。
特に、思考を深める発問や、つまずきへの対応など、具体的な場面を記録しましょう。
道徳の時間の最後の発問「もしあなたがゆう子だったら、このあとどのような行動を取りますか?」。あの発問で一気に子どもたちの思考が動き出したのがわかりました。「道徳を教材の中だけで終わらせない」というのは、こういうことだったのかと勉強になりました。来週させていただく道徳の授業では、教材から抜け出すような発問ができるよう、今のうちから教材研究を進めたいと思います。
視点②:板書について
板書の構造や、児童生徒の発言の取り上げ方などを観察します。
また、板書の時間配分や、視覚的な工夫なども重要な視点です。
本日の算数の授業で、一つの問題に対する複数の解き方を板書する際、色チョークを活用して児童の考えを整理されていました。特に印象的だったのは、「みんなの考え」というコーナーを黒板の右側に設け、そこに児童から出てきた解法を青・黄・赤のチョークで区別しながら書いていかれたことです。その結果、「他の人の考え方がわかりやすい」という児童の声が聞かれ、お互いの考えを共有し学び合う雰囲気が生まれていることに気付きました。板書は単なる記録ではなく、思考を整理し、学び合いを促進するための重要なツールになるのだと実感しました。次回の社会科の授業では、私も色分けを工夫し、「原因」と「結果」を視覚的に区別できる板書を心がけたいと思います。
視点③:学習プリント・ノートについて
学習プリントの構成や、児童生徒の理解を促すノート工夫を観察します。
また、プリントの使用タイミングや、ノート指導の方法なども記録しましょう。
国語の授業で、教科書本文の横に付箋を貼れるようになっている学習プリントが配布されました。児童は、登場人物の心情が表れている言葉を見つけると付箋に書き込み、その部分に貼っていきました。すると、普段はあまり発言しない児童も、自分の見つけた表現について積極的に発表するようになっていったのが印象的でした。このことから、自分の考えを外に出して可視化できる教材は、児童の主体的な学習参加を促すきっかけになるのだと気付かされました。来週担当する物語文の授業では、私も同様の付箋スペースを設けたプリントを作成し、さらに「なぜその言葉からそう感じたのか」という理由を書く欄も追加して、より深い読みにつなげていきたいと思います。
視点④:時間配分について
授業の展開における時間配分や、予定変更への対応などを観察します。
特に、児童生徒の理解度に応じた柔軟な対応について注目します。
本日の理科の実験授業で、電気回路の作成に予想以上に時間がかかってしまう班が多く出ました。担当の先生は、進度の速い班には「どうしてうまくいったのかな?」というワークシートの発展的な問いに取り組ませ、遅れている班にはさりげなくアドバイスをされていました。その結果、予定時間を5分超過したものの、全ての班が実験を完了し、かつ理解度にも大きな差が生じることなく授業を終えることができました。このことから、時間配分は単に計画通りに進めることではなく、児童一人一人の学びを保障するための柔軟な調整が重要だと実感しました。次回の実験授業では、私もワークシートに基本課題と発展課題を設定し、進度に差が出ても全員が充実した学習活動ができるような時間配分を心がけたいと思います。
視点⑤:その他手立てについて
ICTの活用や、グループ活動の進め方など、様々な指導技術を観察します。
効果的だった指導方法は、具体的に記録しておきましょう。
社会科の授業で、タブレットを使って各グループが調べた地域の特産品を、オンラインホワイトボードに集約していく活動が行われました。教室前方のスクリーンには各グループの調べた内容がリアルタイムで表示され、「あ、私たちの地域と似ているね」「なぜこの特産品が生まれたのかな」など、自然と地域間の比較や背景への探究に発展していく様子が見られました。ICTを活用することで、個別の学びをクラス全体で共有し、さらに深い学びへと発展させられることを学びました。来週担当する歴史の授業では、私も生徒が調べた各時代の特徴をオンラインホワイトボードで共有し、時代ごとの比較や変遷を視覚的に捉えられる活動を計画したいと思います。
視点⑥:子どもの様子について
学習意欲や理解度、つまずきの場面など、児童生徒の反応を詳しく観察します。
算数の文章題を解く場面で、普段は積極的なAさんが机に伏せてしまう様子が見られました。近くで様子を見ていると、文章の意味を理解することに苦手意識があるようでした。担任の先生は、Aさんに「まずは問題文の中にある数字に線を引いてみようか」と声をかけ、できたら褒め、次は「これは何個あるっていう数字かな?」と、段階を追って支援されていました。その結果、Aさんは少しずつ自信を取り戻し、最後は「わかった!」と笑顔で問題に取り組めるようになりました。このことから、つまずきのある児童に対しては、できる部分から始めて、小さな成功体験を積み重ねていくことが大切だと気付きました。来週の授業では、私も児童の様子をよく観察し、つまずきが見られた際は、できることから段階的に支援できるよう、事前に支援の手順を考えておきたいと思います。
児童生徒との関わりでの視点
教育実習に書ける気付きは「授業見学」だけではありません。
日々の児童生徒との関わりの中での気づき・考察も書くことができます。
特に、児童生徒のことを理解する力は、教員になってからもとても役立つスキルとなるので、教育実習中からその力を磨いておきたいですね。
以下の視点から、児童生徒との関わりについて捉えてみましょう。
視点⑦:子ども同士の人間関係についての考察
グループ活動や休み時間での関わりを観察し、学級の人間関係について考察します。
休み時間、教室の後ろで一人で本を読んでいたBさんに、普段から活発なCさんが「一緒に遊ぼう」と声をかける場面がありました。最初は戸惑っていたBさんでしたが、Cさんが「この本面白そう!私も読んでみたい」と関心を示すと、少しずつ表情が和らぎ、二人で本の感想を語り合う姿が見られました。その後、他の児童も加わり、休み時間に「読書会」のような雰囲気が自然と生まれていきました。このことから、クラスには積極的に他者と関わろうとする児童と、自分の世界を大切にする児童が共存しており、互いの興味関心をきっかけに関係性を築いていけることを学びました。今後は、授業中のグループ分けの際も、このような自然な関わり合いが生まれやすい組み合わせを意識して考えていきたいと思います。
視点⑧:子ども同士のトラブルについて
トラブルの原因や、教師の介入方法、解決までの過程を記録します。
昨日の給食時間、Dさんが「自分のおかずを勝手に取られた」と涙ぐむ場面がありました。担任の先生は、まず双方の言い分を個別に聞かれ、取ったとされるEさんは「Dさんが『いらない』と言ったから」と主張していました。先生は休み時間に二人を呼び、「相手の気持ちを考えながら、どうすれば良かったか」を考えさせ、互いの思いを伝え合う時間を設けられました。その結果、「いらない」と言われても確認が必要だったことや、はっきりと意思を伝えることの大切さに気付いた様子でした。このことから、トラブルの解決には、単に善悪を判断するのではなく、互いの認識の違いを理解し合う過程が重要だと学びました。今後、私が当事者間の仲裁に入る機会があれば、まず双方の思いをしっかりと受け止め、対話を通じて相互理解に導けるよう心がけたいと思います。
視点⑨:子どもと上手く関われたことについて
コミュニケーションが上手くいった場面や、信頼関係を築けた瞬間を具体的に記録します。
朝の会で、係活動の発表を終えたFさんが「もっと上手に発表できるようになりたい」と話しかけてきました。私は「今日の発表のどんなところを改善したいと思った?」と尋ね、Fさんの思いに耳を傾けました。すると「声が小さくて、後ろの人に聞こえていなかったと思う」と具体的な課題を話してくれ、一緒に練習する時間を設けることになりました。休み時間に教室の後ろに立って練習したところ、徐々に自信がついてきた様子で、次の日の朝の会では、堂々と大きな声で発表する姿が見られました。このことから、児童が自ら気づいた課題に寄り添い、具体的な改善方法を一緒に考えることで、信頼関係が深まることを実感しました。今後も、児童が自分の思いを安心して話せる関係性を築けるよう、まずは丁寧に話を聴く姿勢を大切にしていきたいと思います。
視点⑩:子どもと上手く関われなかったことについて
困難を感じた場面や、その原因について考察します。
授業中、指示を聞かずに離席を繰り返すGさんに対して、「席に戻ろうね」と何度も声をかけましたが、なかなか落ち着かない状況が続きました。私の声かけが強い口調になってしまったせいか、Gさんは「うるさいな」とつぶやき、さらに教室の後ろへ移動してしまいました。担任の先生は、まずGさんの気持ちを受け止め、「今どんな気持ち?」と静かに尋ね、しばらく話を聞いた後で、一緒に席まで戻られました。この出来事から、問題行動への即時の是正ばかりを求めるのではなく、その行動の背景にある児童の気持ちに目を向けることの大切さを痛感しました。次回からは、まず児童の心理状態を理解しようと努め、そのうえで適切な声かけや対応ができるよう、担任の先生の指導方法をさらに学んでいきたいと思います。
授業づくりでの視点
授業準備の過程も、学びの記録として大切です。
以下のような視点で、授業づくりのときの思考を記録に残しておくとよいでしょう。
視点⑪:教材研究での悩みを書く
教材理解や指導方法の選択など、準備段階での課題を記録します。
来週実施予定の6年生社会科「江戸時代の文化」の教材研究を進めていますが、浮世絵や歌舞伎といった伝統文化を、現代の児童の生活とどう結びつけて伝えるべきか、悩んでいます。担当教諭に相談したところ、「当時の人々の暮らしの中での楽しみ方」という視点を提案していただき、現代の娯楽との比較を通じて考えさせてはどうかとアドバイスをいただきました。このことから、歴史学習において重要なのは、単に事実を教えることではなく、当時の人々の生活感覚を現代と結びつけて考えられるような工夫なのだと気付きました。明日は図書室で江戸時代の庶民の暮らしについての資料を調べ、児童が「自分事」として捉えられる導入の工夫を考えていきたいと思います。
視点⑫:教材研究でわかったこと・理解できたことを書く
教材研究を通じて得られた新しい知見や気づきを記録します。
明日の理科「水溶液の性質」の実験準備をしていた際、指導書に載っている実験手順を実際に試してみると、リトマス試験紙の色の変化が教科書ほど明確ではないことに気がつきました。〇〇先生に相談すると、「水溶液の濃度を少し濃くすると、色の変化が分かりやすくなりますよ」とアドバイスをいただき、実際に調整してみたところ、確かに変化がはっきりと確認できました。このことから、教科書や指導書の内容をそのまま行うだけでなく、実際に試してみて、児童の理解を助ける工夫を加えることの重要性を学びました。来週の「水溶液の中和」の実験では、今回の経験を活かし、事前に何度か実験を行い、最適な条件を見つけ出してから授業に臨みたいと思います。
視点⑬:教材研究でアドバイスをもらったことについて書く
指導教員からのアドバイスとその意図を記録します。
明日の国語「読むこと」の授業について指導案を見ていただいた際、「発問が多すぎるかもしれませんね」と〇〇先生からご指摘を受けました。「どの場面で児童に最も考えてほしいのか」という観点から一緒に指導案を見直していくと、確かに本時のねらいに直結しない発問が複数あることに気付きました。「たくさんの発問で児童の思考を促そうとするのではなく、核となる1つか2つの発問で深く考えさせることが大切」というアドバイスをいただき、授業の本質を見失わないことの重要性を実感しました。今晩は指導案を修正し、中心発問に時間をかけられる展開を考え直したいと思います。
視点⑭:授業でやってみたい手立てについて書く
研究や観察を通じて思いついた指導アイデアを記録します。
本日の研究授業参観で、5年生の算数「円の面積」の導入場面において、実際の円形の物を児童に提示し、その面積を求める方法を考えさせる活動が印象的でした。3年生の「三角形の面積」の授業でも、この考え方を応用できないかと考えました。校庭にある三角形の花壇を題材に、「この花壇に種をまくために必要な土の量を求めよう」という実生活と結びついた課題を提示し、面積を求める必要性を実感させられるのではないかと気付きました。三角形の面積の学習は、ともすると公式の暗記に終始してしまいがちですが、生活の中での必要性と結びつけることで、より深い理解につながるのではないかと考えました。明日の指導案作成では、この考えを具体化し、児童が主体的に問題解決に取り組める展開を考えていきたいと思います。
授業実践での視点
自身の授業実践について、以下の視点から振り返ります。
視点⑮発問について書く
計画した発問の効果や、発問の意図を記録します。
算数の「面積」の授業で、複合図形の求積方法を考える場面での発問「この図形の面積はどうやって求められますか?」が、児童にとって抽象的すぎたことに気付きました。多くの児童が戸惑い、手が挙がらない状況が続きました。その後、即興的に「この形をどんな形に分けられそうですか?」と言い換えてみましたが、依然として反応は乏しく、結局教師主導の説明になってしまいました。最初の発問の段階で、図形を指しながら「この形を知っている形に分けられそうな場所はありますか?」とより具体的に問いかけ、児童が見通しを持ちやすいようにすべきでした。また、ワークシートに補助線を引く活動を取り入れるなど、思考の手がかりを視覚的に示す工夫が必要だったと反省しています。次回は、発問を具体的にすることに加えて、児童が自分で考えるための足場かけとなる教材の準備をしっかりしていきたいと思います。
視点⑯板書について書く
板書計画との差異や、実際の効果を振り返ります。
社会科の「米作りのくふうと努力」の授業で、計画していた板書の構造的な配置が、実際の展開では上手く機能しませんでした。当初は左側に農家の方の働きを、右側に地域や自然との関わりを分けて書く予定でしたが、児童から「農家の人が地域の人と協力して水の管理をしている」という意見が出た時、どちらに書くべきか迷ってしまい、板書が混乱してしまいました。また、急いで板書をしようとして字が乱れ、後ろの席の児童から「見えにくい」という声が上がりました。本時の学習課題「なぜ農家の方は、手間と時間をかけて米作りをしているのだろう」は赤チョークで強調したものの、重要な児童の気づきをメモ書き程度の扱いにしてしまい、考えを深める手がかりとして十分に活用できませんでした。次回は、予想される児童の意見と板書の位置関係を事前に整理し、どんな意見が出ても構造的に整理できる余白を確保しておきたいと思います。また、板書の文字の大きさや色遣いにも気を配り、全ての児童が見やすく、思考の整理に役立つ板書にしていきたいと思います。
視点⑰学習プリント・ノートについて書く
教材の効果や改善点を記録します。
理科の「もののとけ方」の実験結果をまとめるワークシートで課題が見つかりました。実験の結果を記入する表は設けましたが、「温度による溶け方の違い」を予想する欄を設けていなかったため、児童が自分の予想と結果を比較しながら考察することができませんでした。また、「気づいたこと」を書く欄が大きすぎて、何を書けばよいのか戸惑う児童が多く見られました。反対に、「実験から分かったこと」を書く欄が狭く、溶け方の規則性について十分に記述できない児童もいました。ある児童が余白に温度と溶ける量の関係を自主的にグラフ化していたことから、そのような表現方法も有効だと気付かされました。今後は、予想→結果→考察の流れが明確になるようシートを改善し、グラフなど多様な表現方法も取り入れられる工夫をしたいと思います。さらに、次時の学習につながるよう、疑問に思ったことを書き留める欄も設けていきたいと思います。
視点⑱:時間配分について書く
予定との差異や、調整の判断について振り返ります。
体育の「マット運動」の授業で、導入の準備運動に予定よりも時間がかかってしまいました。児童の安全面を考慮して、補助倒立の練習を丁寧に行おうとしたため、計画では10分の予定が17分ほどかかってしまいました。その結果、グループ練習の時間が短くなり、後転の技能向上のために必要な繰り返し練習の機会が十分に確保できませんでした。最後の振り返りの時間も3分程度しか取れず、児童の気づきや成果を共有する時間が不足してしまいました。ただ、丁寧な準備運動により、練習中の怪我を防ぐことができ、児童が安心して活動に取り組める環境は作れたと思います。次回は、準備運動の内容を精選し、特に重要な部分に絞って行うことで、メインの活動時間を確保したいと思います。また、活動の区切りごとに時計を確認する習慣をつけ、必要に応じて活動時間を調整できるようにしていきたいと思います。
視点⑲:その他手立てについて書く
様々な指導技術の効果を検証します。
音楽の「リコーダーで音楽づくり」の授業で、つまずきのある児童への個別支援の方法に課題が残りました。練習時間では、上手く音が出ない児童に「息を強く吹いてごらん」と声をかけましたが、かえって力みすぎてしまい、望ましい音色が出せない状況が続きました。他の児童の演奏を聴く機会を設けたものの、「どこが違うのかな?」という漠然とした声かけに留まり、具体的な改善につながりませんでした。しかし、休み時間に「リコーダーの先生」という役割カードを付けた児童が、つまずいている友達に「最初は弱く吹いて、だんだん強くしてみよう」とアドバイスする場面があり、これが効果的だと気付かされました。次回は、児童同士の学び合いを促す手立てとして、技能面でのポイントを視覚化したチェックカードを用意し、互いの演奏を具体的な観点で聴き合える環境を作っていきたいと思います。
視点⑳:子どもの様子について書く
学習活動への反応や理解度を記録します。
国語の「スピーチをしよう」の授業で、児童の反応に大きな個人差が見られました。普段から発表が得意な児童たちは、「夏休みの思い出」というテーマで具体的なエピソードを交えながら、2分間の持ち時間いっぱい話すことができました。一方で、約3分の1の児童は、メモを見ながらでも30秒程度しか話せず、「もう話すことがありません」と途中で止まってしまいました。特に印象的だったのは、普段は積極的にクラスで発言するA君が、全体の前での発表になると声が小さくなり、原稿用紙を手で震わせながら話していた様子でした。しかし、グループでの練習時には、少人数だと安心してよく話せていたことから、段階的な発表の場の設定が必要だと感じました。また、聞き手の児童からの質問や感想が、話し手の自信につながっている場面も見られました。次回は、話す時間や内容の量に幅を持たせ、児童の実態に応じた目標設定ができるよう工夫していきたいと思います。
教育実習日誌の具体的な文例

それでは、教育実習日誌の具体的な文例をいくつか紹介します。
初日の文例
〈今日の目標〉クラスの児童全員に話しかけて、名前を覚える
〈実習内容〉
朝の会では5年2組で自己紹介をしました。準備していた自己紹介クイズに子どもたちが乗ってくれたので楽しく過ごすことができました。1時間目〜4時間目は、5年2組で授業参観をしました。〇〇先生の指示の出し方は「短く」「わかりやすい」ので、子どもたちが迷うことなく動けていました。昼休みは外でドッジボールをして、子どもたちとの仲を深めました。
〈気づき・感想〉
本日の実習を通じて、特に印象的だったのは担任の○○先生の児童との関わり方です。「児童と接するときには、一人一人の名前を呼び、視線を合わせながら声をかける」「指示は短くわかりやすく」「休み時間には児童と一緒に校庭で遊ぶ」児童との信頼関係の構築を大切にしながら学級経営されていることが伝わってきました。
学級を上手く回していくためには、子どもたちとの信頼関係を構築することが大切なんだと実感し、さらに、どのようにして構築したらいいのかが少し見えたように感じます。
〈取り入れたいこと〉
今日の目標である「クラスの児童全員に話しかける」は達成できましたが、名前を全員覚えることはできませんでした。明日からは、児童の名前を覚えることを第一の目標とし、休み時間等も積極的に交流を図っていきたいと思います。そして、◯◯先生のように、子どもたちとの信頼関係を大切にする関わり方を実践していきたいです。
〈今日の目標〉
・学校の1日の流れを把握し、教職員の方々や配属クラスの児童と顔合わせをする
・実習中の諸注意事項を確認し、理解する
〈実習内容〉
朝8時に学校に到着し、教頭先生から学校案内と諸注意事項の説明を受けました。その後、職員朝礼で教職員の方々に紹介していただき、配属クラスの6年1組で自己紹介をさせていただきました。1〜4時間目は担任の☆☆先生の授業を参観し、休み時間には児童たちと交流を図りました。5時間目には実習担当の先生から今後のスケジュールについての説明があり、放課後は職員室で明日の予定確認と教材研究を行いました。
〈気づき・感想〉
初めての実習で緊張していましたが、☆☆先生をはじめ教職員の方々が温かく迎えてくださり、児童たちも積極的に話しかけてくれて嬉しく思いました。授業参観では、☆☆先生の指導方法に多くの学びがありました。特に印象的だったのは、教室全体に目を配りながらも、一人一人の様子をしっかりと観察されている点です。また、授業中の私語に対して、その場で厳しく叱るのではなく、「○○さんの意見、みんなにも聞かせてあげようか?」と、建設的な声かけをされていました。このような対応により、児童たちが前向きに授業に参加できる雰囲気が作られているのだと感じました。
〈取り入れたいこと〉
明日からは、☆☆先生の教室管理の方法を意識的に観察し、特に以下の2点を学んでいきたいと思います。
1.児童全員に目を配りながらも、個々の様子をしっかりと把握する方法
2.問題行動に対する建設的な声かけの具体的な例
また、実習期間中の目標として、児童一人一人の名前と特徴を早めに覚え、積極的にコミュニケーションを取っていきたいと思います。そのために、休み時間も児童と関わる時間を大切にしていきます。
授業観察の文例
〈今日の目標〉
物語文の読解指導における発問の工夫と、児童の読解力を深める指導方法を学ぶ
〈実習内容〉
3時間目に6年1組で行われた国語科「やまなし」(宮沢賢治)の授業を観察しました。本時は物語の後半部分を扱い、かにの兄弟の会話や情景描写から作者の意図を読み取る展開でした。児童たちは4人グループで話し合い活動を行い、その後全体で意見を共有しました。板書を写真に撮り、◇◇先生の発問や児童の反応をメモしました。
〈気づき・感想〉
本日の授業観察を通じて、特に印象的だったのは◇◇先生の段階的な発問の組み立て方です。「かにの兄弟は何を見つめていたのでしょう」という事実確認の質問から始まり、「なぜ『青いやまなし』は『水の中の空』に映っていたのでしょう」という解釈を問う質問へと深めていきました。また、児童が答えに窮した際には、「本文のどの言葉からそう考えましたか」と根拠を問い直すことで、児童自身が文章に立ち返って考えられるよう促していました。グループ活動では、考えが異なる児童同士を意図的に組ませることで、多様な解釈が生まれ、読みが深まっていく様子が見られました。特に効果的だと感じたのは、教師が正解を急いで示すのではなく、児童の意見を板書に整理しながら、クラス全体で考えを発展させていく指導方法でした。
〈取り入れたいこと〉
来週の私の授業実践では、以下の3点を意識して取り入れていきたいと思います。
1.事実確認から解釈へと段階的に深まる発問の構成
2.「本文のどこからそう考えた?」と根拠を問い直す声かけ
3.多様な意見を板書で可視化し、考えを発展させる手法
また、グループ活動を取り入れる際は、◇◇先生のように児童の特性を考慮したグループ分けを工夫し、活発な意見交換が生まれるよう配慮していきたいと思います。
授業実践の文例
〈今日の目標〉
説明文「生き物は円柱形」の学習で、文章構成を意識させながら要旨をまとめる力を育てる
〈実習・活動内容〉
6年1組で説明文の授業を行いました。導入では生き物の写真を提示し、「なぜ円柱形なのか」という発問から始めました。展開では、段落ごとに重要な情報を付箋で書き出し、それを基に文章構造を図式化する活動を行いました。
〈上手くいったこと・上手くいかなかったこと〉
【上手くいった点】
・写真を使った導入で、児童の興味関心を高められた
・付箋を活用した活動により、文章構造が視覚的に理解しやすかった
【課題点】
・発問の意図が明確でなく、児童が戸惑う場面があった
・板書が整理されておらず、後半は見にくくなってしまった
〈感想・考察〉
教材研究は十分に行いましたが、発問の仕方に課題が残りました。特に「筆者の主張」を考えさせる場面では、質問の意図が伝わりにくく、児童の回答にばらつきが出てしまいました。板書も後半になるにつれて雑然としてしまい、学習の流れが分かりにくくなってしまいました。
〈自己反省・改善目標〉
発問は事前に指導案に明確に記載し、意図を整理する
板書計画を作成し、黒板の使い方を工夫する
児童の予想される反応をより詳細に想定しておく
最終日の文例
〈今日の目標〉
・最後の授業実践で、これまでの学びを活かした充実した授業を行う
・実習でお世話になったすべての方々への感謝の気持ちを伝える
〈実習・活動内容〉
朝の会では、児童たちと3週間の思い出を振り返りました。2時間目に6年1組で国語「やまなし」の授業実践を行いました。物語の結末に込められた作者の思いについて、児童たちが活発に意見を交わしてくれました。3時間目は担任の★★先生から授業の講評をいただき、4時間目は学級事務の引き継ぎを行いました。5時間目は、児童たちが企画してくれたお別れ会に参加し、心のこもったメッセージカードや合唱をいただきました。放課後は、校長先生、教頭先生、実習担当の先生方に最終のご挨拶をさせていただきました。
〈上手くいったこと・上手くいかなかったこと〉
【上手くいった点】
・最後の授業では、3週間で築いた児童との信頼関係を活かし、深い読み取りにつながる話し合いができた
・一人一人の考えを大切にしながら、クラス全体で意見を共有する場面を作れた
【課題点】
・感動的な場面での児童の発言に対して、もう少し掘り下げる発問ができれば、より深い学びにつながったと思う
・板書が後半やや雑然となってしまった
〈感想・考察〉
3週間の実習を通じて、教師としての基礎を学ばせていただきました。特に印象的だったのは、児童との信頼関係の大切さです。実習開始時は緊張して上手く関われなかった児童とも、日々の関わりを重ねることで打ち解けることができ、それが今日の授業での活発な意見交換にもつながったと感じています。お別れ会では、児童たちからたくさんの感謝の言葉をもらい、教師という仕事の素晴らしさを改めて実感しました。
〈自己反省・改善目標〉
この3週間の経験を通じて、以下の点を今後の課題として認識しました。
発問の工夫:児童の思考を深める効果的な発問力の向上
板書技術:見やすく、学習の流れが分かる板書の習得
児童理解:一人一人の特性を把握し、適切な支援ができる指導力の向上
教育実習で得た学びと課題を胸に、教員採用試験に向けて一層努力していきたいと思います。最後に、ご指導いただいた★★先生をはじめ、教職員の皆様、そして児童のみなさんに心より感謝申し上げます。
まとめ:教育実習日誌の書き方コツ&ネタを知って、効率よく記録を残そう
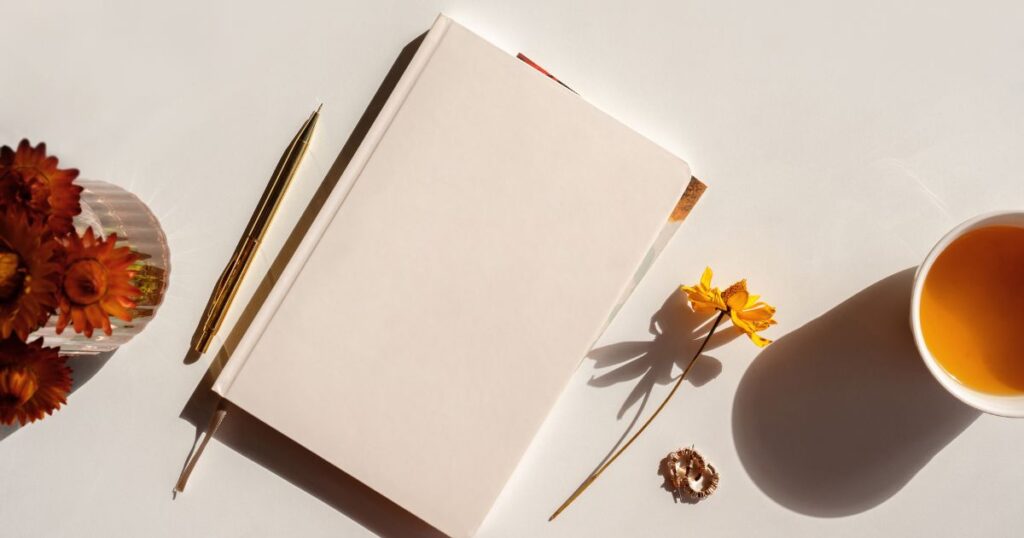
教育実習日誌の書き方について紹介してきました。
まとめると、
- 教育実習日誌の目的
- 自身の学びを振り返り、翌日以降の実習に活かすため
- 実習先の先生に学びを報告し、適切なアドバイスを得るため
- 「授業見学・観察の日」の書き方
- 今日の目標
- 実習・活動内容
- 気づき、学びになったこと
- 感想・考察
- 取り入れたいこと・代替案・アクションプラン
- 「授業実践の日」の書き方
- 今日の目標
- 実習・活動内容
- 上手くいったこと・上手くいかなかったこと
- 感想・考察
- 自己反省・改善目標・アクションプラン
- 効果的な書き方のコツ
- 前日のうちに「今日の目標」を書く
- こまめにメモを取りながら記録する
- できるだけ勤務時間内に提出する
- ネタ切れしない20の観察視点
- 授業見学での視点(発問、板書、教材等)
- 児童生徒との関わりでの視点(人間関係、トラブル対応等)
- 授業づくりでの視点(教材研究、アドバイス等)
- 授業実践での視点(実践の振り返り、改善点等)
教育実習日誌は単なる記録ではなく、教師としての成長につながる重要なツールです。
様々な視点から観察し、具体的に記録することで、より充実した実習になるよう心がけましょう。
教育実習「ノウハウカテゴリ」には、以下の記事があります。
気になる記事をタップで読んでみよう↓
\まとめ記事はこちら/
個別記事