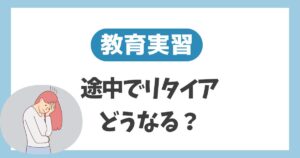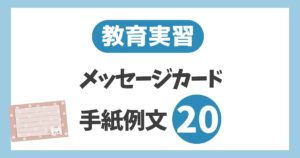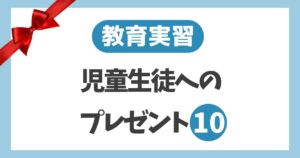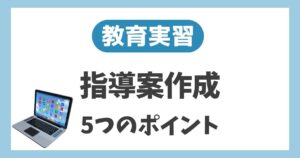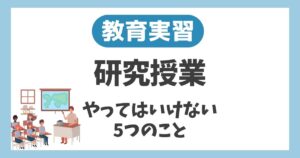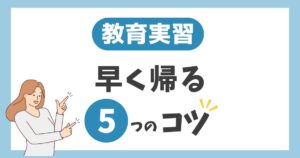教育実習の授業でボロボロ|授業が下手だと思ったときの行動2選
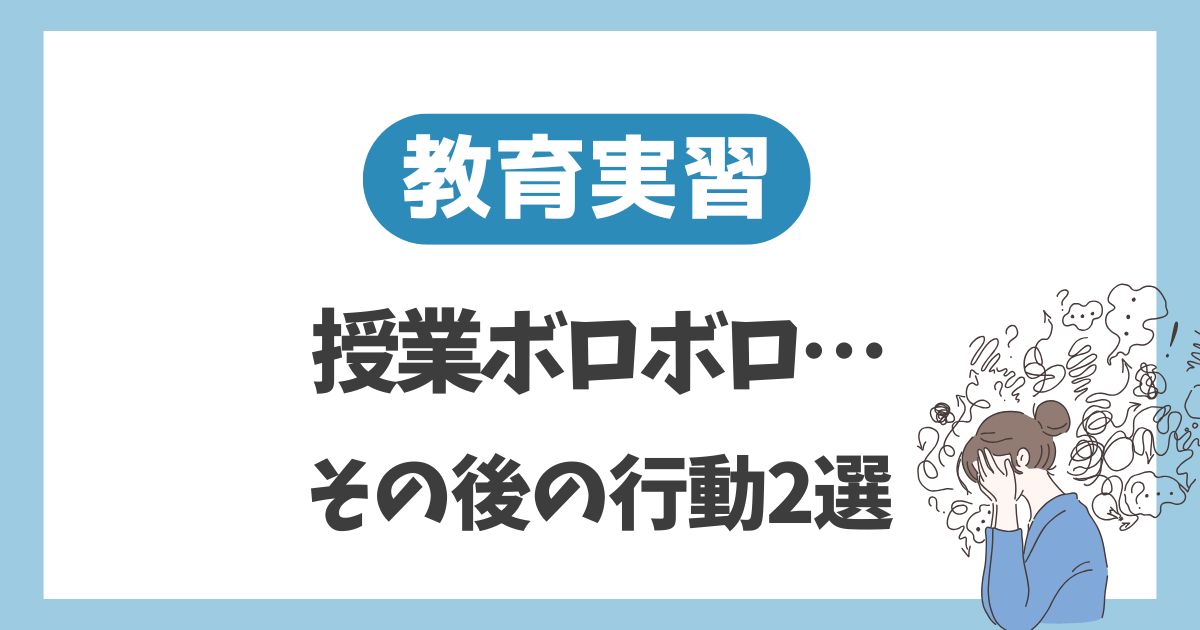
「教育実習でボロボロな授業をしてしまった…」
「どうして自分はこんなに授業が下手なんだろう」
と落ち込んでいる教育実習生の方も多いのではないでしょうか。
念入りに授業の準備をしたつもりでも、実際の授業ではうまくいかないことは、よくあります。
しかし、授業に失敗してしまったら、その後どう気持ちを切り替え、何をすればいいのかがわからなくなりますよね。
特にそれが教育実習の授業だったらなおさら…。
この記事では、教育実習で授業がボロボロだったと感じたときの具体的な対処法と、今後の進路について詳しく解説します。
- 教育実習でボロボロだった授業を改善する方法
- 教員以外の道に進む方法
記事を読むことで、授業改善のヒントが見つかり、自分に合った進路選択ができるようになりますよ。
あわせて読みたい(タップで閉じる)
教育実習の授業がボロボロだったときの行動は2つ

教育実習で授業がうまくいかなかった場合、取るべき行動は大きく分けて2つあります。
一つは授業改善に向けて努力すること。
教育実習での悔しさをバネに授業を改善し、教員への道を目指します。
もう一つは自分の適性を見極め、教員以外の道に進むこと。
自分の適性をいち早く察知することで、あらたな未来の可能性をつかむことができるようになるかもしれません。
どちらを選択するにしても、まずは冷静に状況を分析することが大切です。
- 授業がうまくいかなかった原因は何か
- 改善の余地はあるのか
- そもそも教職が自分に合っているのか
といった点について じっくりと考えてみましょう。
ここからは、「授業改善に向けて努力をすること」「教員以外の道に進むこと」の両方について詳しく見ていきます。
「自分はどっちの道かな…」と考えながら、読み進めてみてくださいね。
教育実習でボロボロだった授業を改善する方法

教育実習でボロボロな授業をやってしまったときの行動1つ目は、「授業を改善すること」です。
授業の失敗により、身も心もボロボロになった状態から、どのように気持ちを切り替えて、どう授業を改善していけばいいのかみていきましょう。
まずは「みんな最初は下手だった」と思う
ボロボロな授業をした後は、誰しも深く落ち込んでしまうもの。
私自身も教育実習中にボロボロな授業をして、かなり落ち込んだ経験があります。
(国語の授業をして、授業のねらいとはまったく違う方向へ行ってしまい、途中で指導教官の先生に交代させられて、後ろで惨めに参観をしました。)
また、教員になってからも保護者が見に来る授業参観日でも散々な授業をしてしまい、かなり自己嫌悪に陥ったこともありました。
そんなときに大切なのは、まずメンタルを整えること。
メンタルが浮上しないことには、何をやっても全くダメですね…。
私がボロボロな授業をやったときに、メンタルを整えた方法は2つあります。
①考え方を切り替える
1つ目は「どんなベテランの先生も、みんな最初は授業が下手だった」と思うようにすること。
いろんな先生に話を聞くと、
「若い頃の授業はかなり悲惨だったよ〜」
「なんなら先週ホントひどい授業をしたばっかり」
など、いろんな失敗授業エピソードを聞くことが出来ます。
つまり、今上手に授業をしている先生方も、みんな「ボロボロな授業」をしてきた経験があるということ。
最初から完璧な授業ができる人なんていません。むしろ、失敗と改善を繰り返すから、少しずつ成長していったのです。
赤ちゃんが歩き方を覚えるまでに、何度も転んで、たくさんの失敗を重ねながら、少しずつ上手に歩けるようになっていくようなもの。
授業力も同じように、経験を積み重ねることで徐々に身についていきます。
むしろ、失敗がなければ、大きく飛躍することなんでできやしないのです。
そう考えることで、モヤモヤして潰れそうになっていたメンタルが、少し回復することでしょう。
②ノートに感情を書きなぐる
2つ目は、感情を整理するためにノートに気持ちを書き殴ることです。
「むしゃくしゃしている気持ち」
「不甲斐ない自分」
「なぜ事前にもっと指導してくれなかったのかという悲しみ」
「悔しい思い」
「今後どうなりたいかという思い」
など、自分の思いをすべてノートに書き殴ります。
書くことがなくなるまで何ページでも書きます。
すると、ノートを書き終えるときには頭がスッキリし、次に自分が何をすべきなのかがはっきりと見えてきます。
最後に書き出した内容を「自分で解決できること」と「自分では解決できないこと」に分類してみましょう。
そして、「自分に解決できること」のみに焦点を当てることで、次の具体的な行動へと移れるようになりますよ。
実習中の次の授業を改善する
もしあなたが教育実習中で、まだ授業をするチャンスがあるのなら、次の授業改善に取り組みましょう。
授業改善をするためのポイントは3つ。
①指導教官からのフィードバック
1つ目は、指導教官からのフィードバックを真摯に受け入れること。
指導教官は授業のプロです。
自分の授業を見て感じたことを正直に言ってもらい、その中で改善できそうなことを次の授業でやってみましょう。
アドバイスがいくつもある場合は、1度に全部するのは難しいかもしれません。
そんなときは、「一番効果がありそうなもの」を1つに絞ってやってみるのがよいでしょう。
②指示・説明の仕方の工夫
2つ目は、指示・説明の仕方を学ぶことです。
教育実習生の授業でよくある失敗が「児童生徒に指示・説明がきちんと伝わっていない」ということ。
普段、人前で話すことに慣れていないと、伝わりづらい指示・説明をやってしまいがちになります。
私が意識している指示・説明の仕方の基本は、以下の3つです。
- 結論ファースト
「今から2人組になって話し合います」「これは◯◯が正しいです。なぜなら〜」のように、最初に結論を言います。そうしないと、「今何の話をしているのかわからない」という状態で話を聞き続けないといけないので、聞き手はストレスを感じやすい。 - 見通しを持たせる
「今日は3つの活動をします」「ポイントは3つあります。1つ目は〜、2つ目は〜、3つ目は〜」と、全体の流れを最初に示す。そうすると、子どもは頭の中でカウントを数えながら、指示した内容を覚えてくれる。 - 指示は短く簡潔に
1回の指示は1つだけにし、シンプルな言葉で伝える。複雑な指示・説明は、子どもたちの頭の中に残らない。
この3つを意識するだけでも、子どもが活動しやすい授業になります。
まずは、自分の指示の出し方・説明の仕方がわかりにくいものになっていないか振り返って、改善してみてくださいね。
授業の「不易」な部分を学びたい
教育実習の授業で失敗したくない!
という人は、教育界のベストセラーを読んでおきましょう。
授業の基本をおさえておきたい方は、向山洋一先生の「授業の腕を上げる法則」↓
向山洋一先生というのは、教育界で知らない人はいないほどのレジェンド。
40年前以上前に生み出された本ですが、今でも現役で使える内容ばかりです。
教育実習生・初任者の先生にまず最初におすすめしたい1冊なので、まだ読んだことがない方はこの機会に手に取っておきましょう。
授業以外でも使える「子どもを動かす指示の出し方」を学びたい方は、名著「AさせたいならBと言え」を読んでおきましょう。
教育界で知らない人はいないほどの名著が、30年ぶりに「イラスト図解入り」で読みやすく、わかりやすくなって新登場しました。
小・中・高どの校種でも使える指示の出し方が学べます↓
③教科の本を読む
また、時間に余裕があるなら、自分の指導する教科の本を読むのも効果的です。
(教育実習中に本を買って読む時間的な余裕がある人は少ないと思いますが…)
これまで、多くの先輩の先生方が、実践をまとめて本を出版してくださっています。
その中には、あなたが次に授業をする教科・単元に関わる本が出版されているかもしれません。
1冊でも読めば、授業アイデアやわかりやすい授業展開が学べるので、時間に余裕があるなら手に入れて読むことをおすすめします。
アマゾンや楽天で、
「小学校 国語 大造じいさんとがん」
「中学校 国語 説明文 指導」
など、「校種 教科 指導内容(単元名など)」で検索すると、書籍がヒットしますよ。
自分の査定授業に関わる教科・単元の本を、1冊は探して手元に持っておきましょう。
実習後、教員採用試験までに改善する
教育実習後も、教員を目指すのであれば、授業力の向上のためにできることを進めていきましょう。
というのも、教員採用試験では模擬授業が課されることが多いため、授業力が無ければ試験に落ちやすいです。
教員採用試験までに授業力を高めるには、以下のような取り組みが効果的です。
- 授業力向上に関する専門書を読む
→本屋さんに行ったり、Amazon・楽天市場などを活用して、教育書を読み漁りましょう。
いつの時代でも通用する基本事項が書かれてあるコチラの本は1度読んでおくことをおすすめします。 - 附属学校などの研究授業を見学する
→おすすめは「上手」と評判の先生をリサーチして見ること。
どの先生が「上手」かわからない場合は、現地で人が多く集まっている教室を覗くとよい(有名な先生がやっている可能性大) - 教員向けの授業力向上セミナーに参加する
→SNSなどで情報を集めると、授業力向上セミナーなどが開催されていることも
大学のうちから参加することで、いろんな先生方とのつながれるのでおすすめ
ぜひ、教員採用試験までに、自分の授業力を高めておきましょう。
教育実習の授業がボロボロだったから別の道に進む

ボロボロな授業をしてしまったことから「自分には教職は無理…」と感じたのであれば、別の道を進むのも1つの手です。
教育実習に行ったからと行って、必ずしも教員にならなければならないという決まりはありません。
「教育実習は、教職への適性を見極める大切な機会。そこで自分の適性を見極めることが出来た。」
と割り切って、新たな挑戦をするのもよいでしょう。
教員以外の道に挑戦する場合は、こちらの記事で「その後何をすればいいのか?」について紹介しています↓
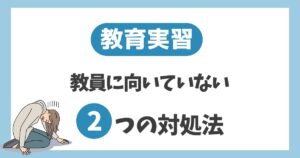
教育実習で教員に向いていないと感じた方は、ぜひこちらの記事も合わせて読んでくださいね。
まとめ:教育実習の授業がボロボロでも、次につなげればオールOK!

教育実習での授業の失敗は、決して恥ずかしいことではありません。
大切なのは、その経験をどう活かすかです。
授業改善に取り組むにせよ、別の道を選ぶにせよ、実習での経験を自己理解と成長のきっかけとして活用していきましょう。
もし、ボロボロな授業をしてしまったことの「心の傷」が一人で癒せそうにない場合は、電話相談サービスを活用するのも1つの手です。
自分のモヤモヤする気持ちは、人に話すことで気持ちが落ち着き、メンタルを回復させられます。
…が、自分の失敗談って、知り合いに相談したくはないですよね…。
でも、電話相談サービスなら「知り合いじゃない人」かつ「聞き方のプロ」なので、授業失敗の悩みも言いやすく・すんなり悩みも解消してくれます。
「一人で抱え込んでいるのがつらい」
「とにかく誰かに相談に乗ってほしい…」
という方は、一度電話相談を活用してみてくださいね↓
電話相談【ココナラ】(初回無料部分があるので安心)
教育実習「ノウハウカテゴリ」には、以下の記事があります。
気になる記事をタップで読んでみよう↓
\まとめ記事はこちら/
個別記事