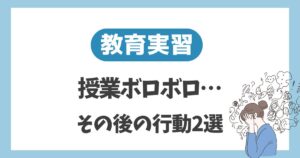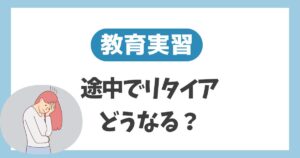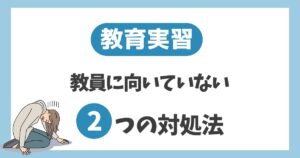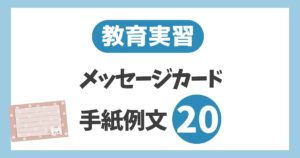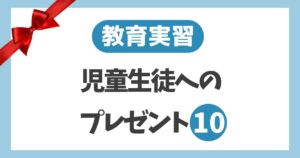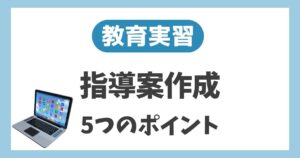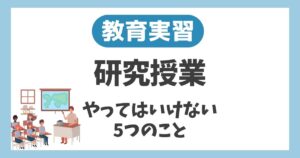教育実習の授業見学のメモ術3選|記録の取り方ポイント
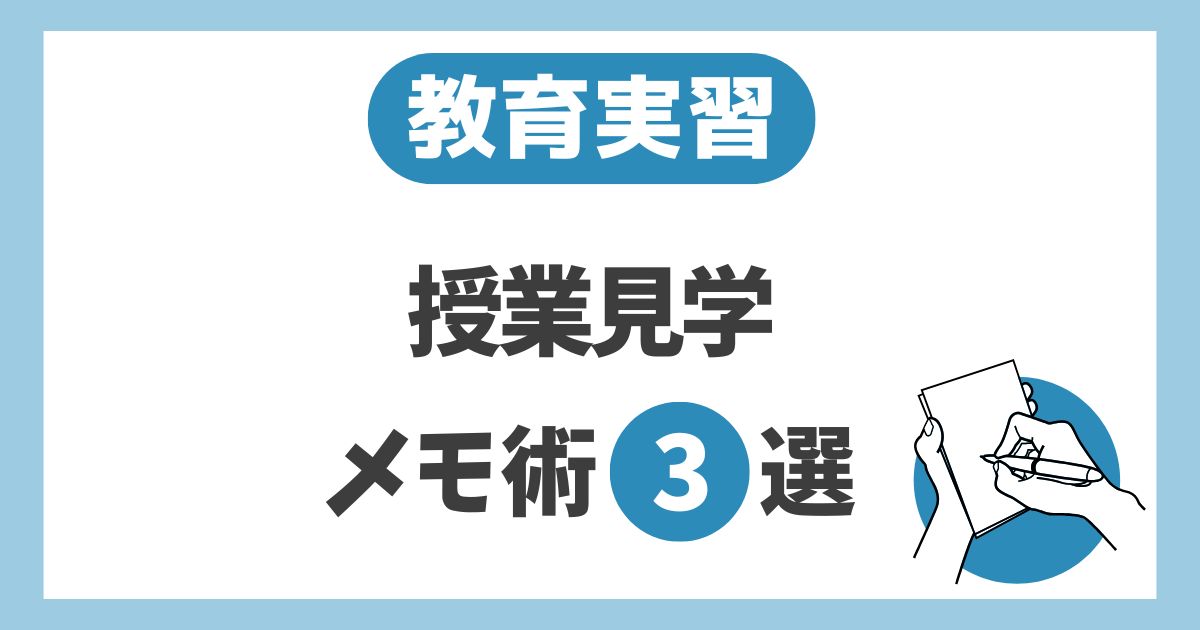
「授業見学のメモってどんなことを書けばいいんだろう?」
「なにをポイントに見ればいいのかな?」
と悩んでいる教育実習生の方も多いのではないでしょうか。
教育実習では、実際に授業を行う前に、指導教員の授業を見学する機会があります。
しかし、何をメモすればいいのか分からず、ただ漫然と授業を見てしまいがちですよね。
実は、授業見学には効率よく・効果的にメモを取る「メモ術」があるのです。
この記事では、教育実習での授業見学でのメモ・記録の取り方ポイントとメモ術3選を紹介します。
- 教育実習のメモの取り方ポイント
- 教育実習のメモ術3選
記事を読むことで、教育実習中の授業見学で学んだこと・メモしたことを、自分の授業に生かせるようになりますよ。
あわせて読みたい(タップで閉じる)
教育実習メモ&記録の取り方ポイント

授業見学での効果的なメモの取り方について、3つのポイントを紹介します。
ポイント①:授業の流れをメモする
授業は「導入」「展開」「終末」という流れで構成されています。
この流れに沿ってメモを取ることで、授業の全体像を把握しやすくなります。
やり方は簡単で、メモを取りながら「導入」「展開」「終末」ごとに横線を引いてメモを区切るのです↓
授業開始からメモを始めて、「あ、そろそろ導入が終わって、展開に入ったかな?」と思ったときに、シューッと横線を引いて区切るような感じでOK。
各段階でメモを区切って書くことで、後から見返したときに授業の流れが思い出しやすくなりますよ。
特に、教育実習中は、「導入」から「展開」へどのように持っていくとスムーズなのかを重点的にメモを取るのがオススメ。
子どもの興味付け〜展開のつなぎがスムーズにできるようになると、授業が組み立てやすくなるので、ぜひ現場の先生の技を学んでおきましょう。
ポイント②:教師の手立てをメモする
「導入」「展開」「終末」で区切りながらメモを取るのはわかったけど、具体的に何のメモを取ればいいの?
と思っている人も多いことでしょう。
まずメモを取りたいのは「教師の手立て」。
うまく授業を進めるために、現場の先生はいろんな「手立て」をしています。
以下のことについてメモを取ることで、あなたの授業へと生かせることがないかを見つけてみましょう。
発問
発問とは、授業中に教師が意図的に行う問いかけや投げかけのこと。
授業中のあらゆる場面で行われる「発問」には、授業力を高めるためのヒントがたくさん詰まっています。
以下のような点に注目してメモを取りましょう↓
- 学年の発達段階に合わせた言葉遣いの工夫
「小1にはこういう言葉づかいじゃないと伝わらないのか…」「小6って結構難しい言葉でも理解できるんだな!」などの発見がありますよ - 導入から展開へと子どもの思考をスムーズに導く発問の仕方
「こういう風に発問したら、興味付け→めあてまでスムーズにもっていけるのか〜!」と感じたものをメモするのがおすすめ - 子どものつぶやきを拾い、クラス全体の学びへと発展させる切り返しの技術
子どもがふとつぶやいた言葉をうまく拾って、授業の展開に生かした発問などがあれば、メモしておきましょう。
また「自分だったらなんて切り返していたかな?」などと考えてみるのも授業力UPにつながるのでおすすめ。 - 効果的な指示の出し方や言葉選び
子どもを動かすときの言葉選びにも多くの工夫がされています。
子どもがスッと行動できた声掛けなどがあればメモしておきましょう。
発問の技術は、授業を行うときに大活躍します。
印象的だった発問は、具体的な言葉遣いまでメモしておくと良いでしょう。
子どもに指示を出して動いてくれるかどうか不安…。
どのように指示を出したらいいのか知りたい!
という人は、名著「AさせたいならBと言え」を読んでおきましょう。
教育界で知らない人はいないほどの名著が、30年ぶりに「イラスト図解入り」で読みやすく、わかりやすくなって新登場しました。
小・中・高どの校種でも使える指示の出し方が学べます↓
また、授業の基本をおさえておきたい方は、向山洋一先生の「授業の腕を上げる法則」を一度読んでおきましょう↓
向山洋一先生というのは、教育界で知らない人はいないほどのレジェンド。
40年前以上前に生み出された本ですが、今でも現役で使える内容ばかりです。
教育実習生・初任者の先生にまず最初におすすめしたい1冊なので、まだ読んだことがない方はこの機会に手に取っておきましょう。
板書
板書もメモを取っておくとよいでしょう。
…といっても、板書に書かれてあることをそのままメモするわけではありませんよ!
板書に書かれてあることは、授業後に「板書の写真を撮らせていただいてもいいですか?」と聞けば、たいてい許可してもらえるので、メモに写す必要はありません。
じゃあ、何をメモしたらいいのか。
以下のことを中心にメモを取りましょう。
- チョークの色の使い分け
→色に何か意味やルールがあるのか?どのように使い分けているのか? - 子どもの発言の取り上げ方
→子どもの発言のどの部分を取り上げるのか? - 板書の構造化の方法
→板書を見やすくする工夫、学習内容を理解しやすくする工夫
板書が上手な先生がいたら、どのようなことを意識して書いているのかを質問してみるのも勉強になりますよ。
プリント・ノート指導など
学習プリントの活用方法や、ノート指導の工夫についても、気づいたことがあったらメモを取っておきましょう。
特に、低学年や、特別支援学級の子がいるクラスのノートの取り方・使い方は、わかりやすく書きやすいような工夫がされていることが多いので、勉強になりますよ。
ちなみに、プリントやノートも板書と同様、書いてあることを一言一句書き写す必要はありません。
授業後に「プリント・ノートの写真を撮らせていただいてもいいですか?」と聞けば、たいてい許可してもらえるので、写真で記録に残しておきましょう。
※ただし、個人情報の取り扱い方には注意が必要です。
教材教具
授業で使用される教材・教具についても、気づきがあった場合はメモを取りましょう。
特に、「具体物を使う算数・数学」、「実験のある理科」などは、教材・教具が違うと教育的な効果がガラリと変わることがあるので、
- なぜこの教材・教具を使ったのかな?
- この教具を使うことで、どのような効果があるのかな?
などを分析しながら、メモを取るといいですね。
ポイント③:子どもの様子をメモする
授業中は先生の発問や板書だけを見ておけばいいんでしょ?
と思っていませんか?
もちろん、教師の発問・板書・ノート指導などを見ることは重要なのですが、それと同じぐらい重要なポイントとして「子どもの様子」が挙げられます。
子どもの何を見ればよいのか。
子どもの表情
まず確認してほしいのが子どもの表情です。
子どもの表情を見ることで、教師の手立てが上手く言っているかどうかが判断できます。
大人から見たら「今の発問めっちゃいい感じ」と思っていても、子どもたちの顔は「ポカーン…」としている、などということはよくあります。
自分が授業するときも、子どもの表情を確認しながら
「今の言い方じゃ伝わってないな…、他の解説を加えるか…」
などと臨機応変に対応するので、授業見学のときから子どもの表情も一緒にチェックするようにしましょう。
子どもの発言
次にチェックしたいのが子どもの発言です。
教師の発問に対して、子どもがどのような発言をするか注目することで、
- 子どもたちの思考に触れられる
→子どもは大人が想定しているとおりに物事を考えているとは限りません。
どのような思考をしているのかに触れることで、授業での発問がうまくなります - 子どもが理解しているかがわかる
→子どもの発言に耳を傾けることで、教師の手立てが効果的であるかどうかがわかります
などがわかります。
子どもの思考や理解度に触れることで、授業づくりの手がかりを得ることができます。
子どもの発言の中で、
「え?そういう内容を答えるのか…!」
「あ〜、確かに今の聞き方だったらそう答えるよね」
といったものがあれば、メモを取っておいて、自分の授業づくりのときに参考にしましょう。
教育実習の授業見学おすすめメモ術3選

さて、ここまで
- 「導入」「展開」「終末」ごとに区切ってメモを取る
- 教師の手立てのメモを取る
- 子どもの様子のメモを取る
ということについてお伝えしてきました。
授業中の様子をメモに書くだけでも十分学習効果はありますが、
実は、さらにメモの効果を高めるメモ術があるのです。
ここでは、おすすめのメモ術3選を紹介します。
メモ術①:自分の考え・疑問をメモに付け足す
授業見学中に感じた疑問や気づき・自分の考えを、メモに書き添えておきましょう。
「なぜこのタイミングでこの発問をしたのだろう?」
「この教材の提示順序にはどんな意図があるのだろう?」
など、授業中に感じた疑問は、メモとセットでどんどん書き加えます。
授業後に、そのことについて考えることで新たな発見につながることもありますし、
「あのタイミングでこの発問をしたのはどのような意図があったのですか?」
「この教材の提示順序にした理由は、私は◯◯を狙ったからだと考えたのですが、実際のところはどうなんでしょうか?」
といったように、後から指導教員に質問して疑問を解消することもできます。
事実だけをメモするのではなく、自分の考え・疑問も一緒にメモしておくことで、授業力が大幅にアップしますよ。
メモ術②:分析的に見る
授業の成功点や改善点を分析的に見ることで、より実践的な学びが得られます。
- 上手く流れた授業を見た場合:今日のどのような手立てが効果的だったのかを考えてメモをする
- 予定通り進まなかった場合:どのような改善をすれば上手くいくのかを考えてメモをする
- 子どもたちの反応が良かった場合:どの手立てが子どもたちの反応を高めたのか考えてメモする
このように、分析的にメモを取ることで、自身の授業実践に活かせる具体的なアイデアが得られます。
また、分析的に見ることができれば、「上手くいっている授業」「うまく流れていない授業」のどちらからでも学びをえることができるようになります。
自分の授業を改善するときにも使える見方なので、ぜひ「分析的に見てメモをする」ということにも挑戦してみてくださいね。
メモ術③:アクションプランを書く
授業見学が終わった後は、メモを見返しながら「アクションプラン」を考えてみましょう。
- 効果的だと感じた指導の中から、自分にできそうなものをピックアップしてまとめてみる
- 実践可能な形に書き換えて、次に自分が授業をするときの行動計画に組み込む
- いつ、どの場面で活用できそうかまで考えてまとめておく
このように、見学で得た学びを自分の実践に落とし込むことで、より効果的な学ぶことができますよ。
教育実習授業見学のメモの取り方でよくある質問

授業見学のメモ取りについて、実習生からよく寄せられる質問をまとめました。
メモを取ることに集中しすぎて、授業の観察がおろそかになってしまいます。
最初は授業の観察を優先し、キーワードレベルでメモを取るようにしましょう。慣れてきたら、観察とメモ取りのバランスを調整していけば大丈夫です。
どのくらいの量のメモを取ればよいですか?
質が重要です。ポイントを絞って、後で見返したときに授業の様子が思い出せる程度のメモを心がけましょう。
まとめ:教育実習の授業見学メモ術で、あなたの授業力をUPさせよう

授業見学でのメモ取りがうまくなると、教育実習での学びが加速します。
- 授業の流れ、教師の手立て、子どもの様子という3つの観点でメモを取る
- 疑問点や気づきを積極的にメモに書き添える
- 分析的な視点を持ち、実践につながるアクションプランを立てる
これらのポイントを意識しながら、授業見学で学んだことを自分の授業に取り入れていきましょう。
教育実習「ノウハウカテゴリ」には、以下の記事があります。
気になる記事をタップで読んでみよう↓
\まとめ記事はこちら/
個別記事