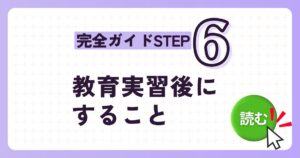【保存版】教育実習中に使えるノウハウ完全ガイド
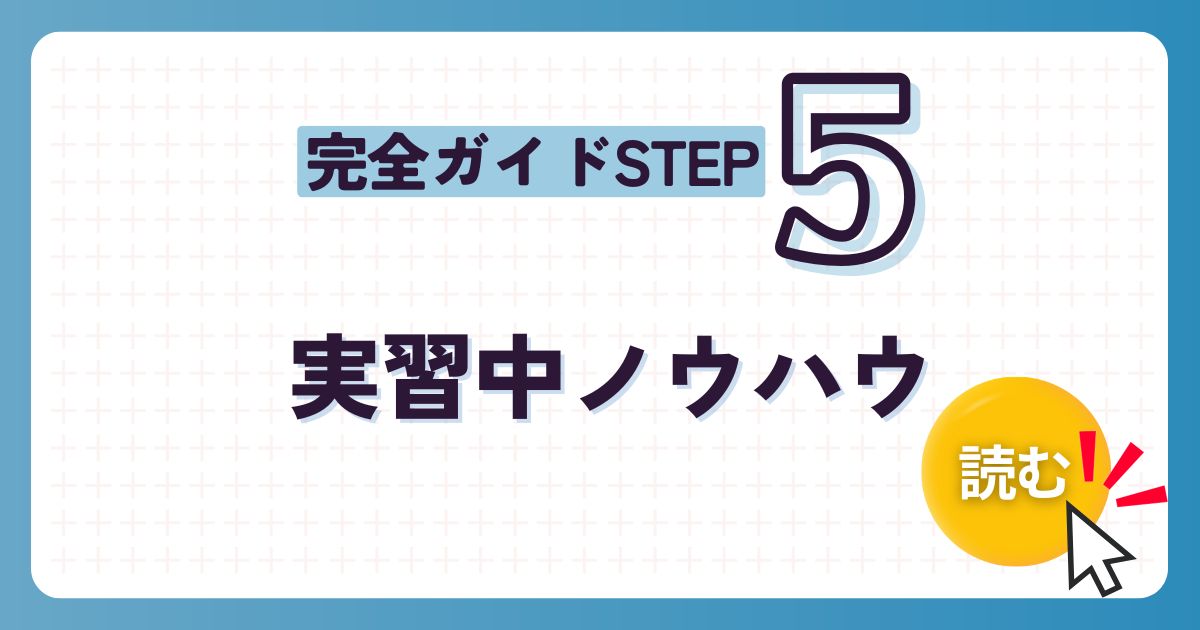
当ブログでは、教育実習の悩みをSTEP1〜6で解決できます。
タップできます
ぜひ参考にしてみてください。
このページでは、「教育実習中に使えるノウハウや気をつけるべきこと」を、わかりやすく丁寧に紹介しています。
詳しく知りたい人向けに、「関連記事(あわせて読みたい)」も準備しているので、ポチポチタップしながら理解を深めていってくださいね。
今すぐ、知りたい情報だけササッと確認したい方は、以下の項目をクリック(タップ)してください↓
それでは、順番に見ていきましょう。
【教育実習】あいさつ・自己紹介ノウハウ
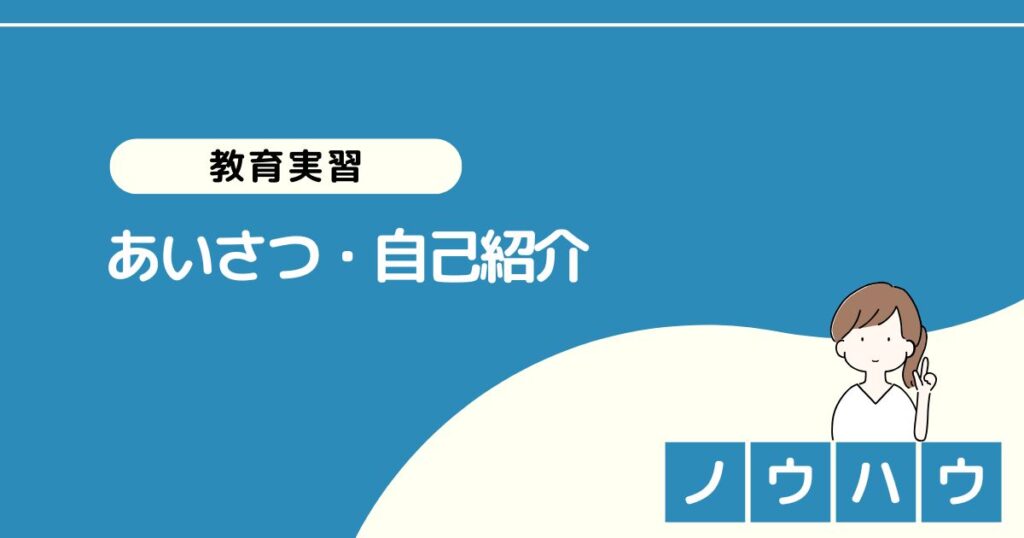
ノウハウ①あいさつ・自己紹介
教育実習がスタートしたら、最初に何をするか知っていますか?
それは、あいさつと自己紹介です。
教育実習では、何度も何度も「あいさつ・自己紹介」をする機会があります。
- 【初日】職員室にて、教職員向けにあいさつ
- 【初日】クラスにて、児童生徒向けにあいさつ
- 【通信】保護者に、学級通信であいさつ
- 【最終日】クラスにて、児童生徒向けに別れのあいさつ
- 【最終日】職員室にて、教職員向けに別れのあいさつ
(他にも、全校集会であいさつをするケースもあります)
教育実習初日のあいさつは、緊張のあまりセリフを忘れてしまって恥をかいてしまうことも…。
教育実習のあいさつや自己紹介の文例を確認しておきたい方はこちらで詳しく紹介しています↓
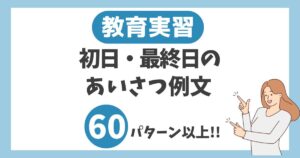
【教育実習】スケジュール・効率ノウハウ
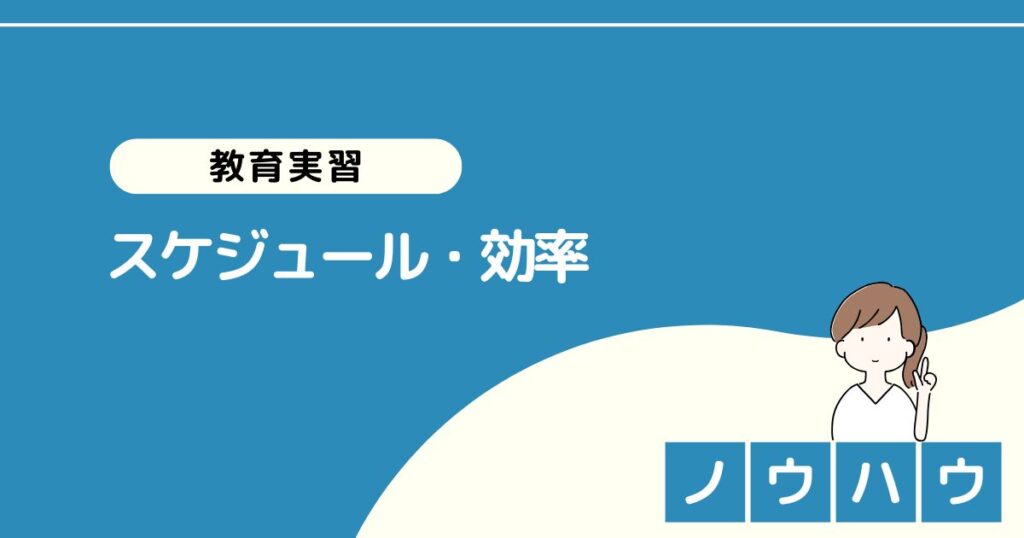
教育実習での業務を効率よくこなすためには、見通しを持っておくことが大切です。
ここでは、教育実習のスケジュール確認と、効率UPして早く帰るためのノウハウを紹介します。
ノウハウ②:教育実習中のスケジュール確認
教育実習は2〜4週間の期間で行われます。
取得する免許によって期間が異なりますが、実は、どの実習でも基本的なスケジュールの流れは共通しています。
教育実習の基本的なスケジュールは、大きくわけて
- 初日:あいさつが中心
- 序盤:学校生活の流れ理解が中心
- 中盤:授業実践開始
- 終盤:研究授業(査定)の準備と実践
- 最終日:お別れのあいさつが中心
の5つの期間に分けることができます。
それぞれの実習期間で、具体的にどのようなスケジュール感になるかを、図解付きでまとめたので、
教育実習のスケジュールを詳しく知りたい方はこちらで確認してくださいね↓
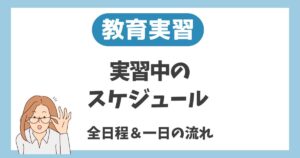
ノウハウ③:早く帰る5つのコツ
教育実習中はするべきことがたくさんあります。
そのため、仕事をテキパキこなして、できるだけ早く家に帰りたいですよね。
教育実習で早く帰るためのコツは5つあります。
- 事前にできる準備をしておく
- 学校でしか出来ないことを優先する
- 早めに相談&7割完成で一旦見せる
- できないことは断る
- メンタルブロックを外す
これらの5つを意識して行動することで、教育実習中だけでなく、教員になってからも早く帰れるようになりますよ。
教育実習で早く帰る5つのコツを詳しく知りたい方は、こちら↓
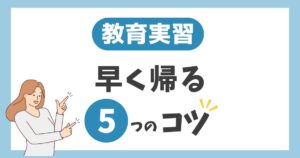
【教育実習】児童生徒とのかかわりノウハウ
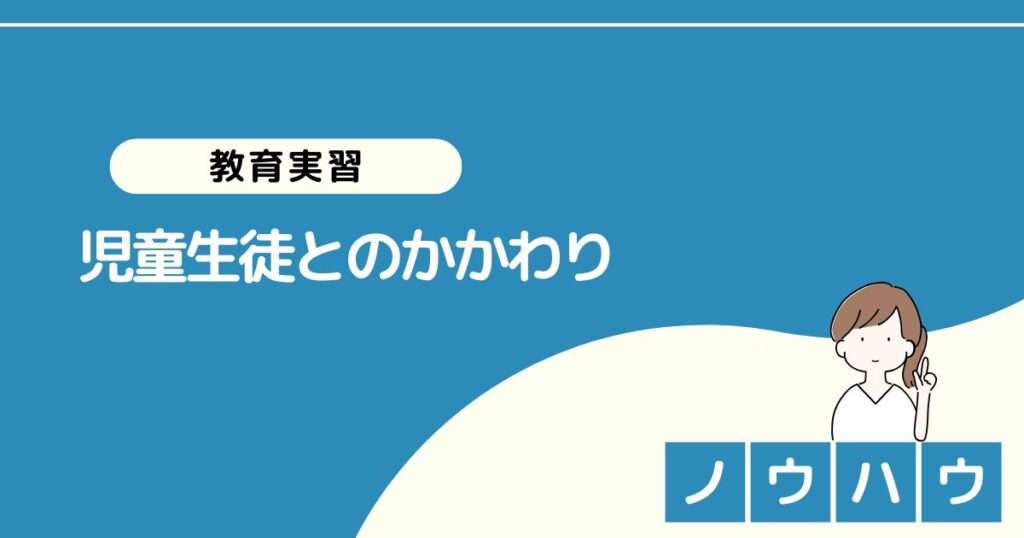
教育実習での重要な要素の1つが「児童生徒との関わり」です。
児童生徒との関わり方が上手く行けば、授業でも上手くいく確率がググっと上がります。
なぜなら、児童生徒があなたのことを好意的に見てくれていたら、授業中のあなたの言葉もスッと入っていくから。
査定授業では「大好きな◯◯(あなた)先生の大事な授業だから、発表いっぱい頑張ったよ!」と言ってくれる子が現れるかもしれません。
それぐらい、児童生徒との関わりは大切です。
ここでは、児童生徒との関わり方のノウハウを紹介します。
ノウハウ④:児童生徒との関わり方のコツ
教育実習では「臆せず話しかける」ことが大事です。
教育実習生の中には「子どもの方から自然と話しかけてくるでしょ?」と思っている人もいますが、全然そんなことありません。
小学校低〜中学年であれば、子どもの方から寄ってくることもありますが、高学年〜中高校生だと、半分以上は話しかけて来てくれません。
そのため、自分から積極的に関わりにいって、つながりを作らなければならないのです。
では、どのように関わっていけばよいのでしょうか。
おすすめは、以下のように関わることです。
- 序盤は「関わりネタ」も使いながら積極的に仲良くなる
- 名前覚えクイズ
- 好きな◯◯を聞く
- 一緒に遊ぶ
- 中盤以降は、しっかりと距離感を意識しながら関わる
- 必要に応じて毅然とした態度で指導
- 常に丁寧な言葉づかいを心がける
- まんべんなくコミュニケーションを取る
詳細については、教育実習で児童生徒との関わリ方のコツにまとめているので、チェックしてみてください↓
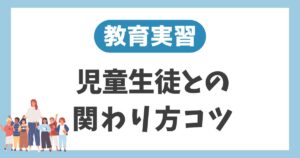
ノウハウ⑤:朝の会・ホームルームのネタ15選
教育実習が序盤〜中盤に差し掛かると、朝の会やホームルームの進行をお願いされることがあります。
そのときに悩むのが「教育実習生の話」。
初日はいいかもしれませんが、3日・4日と続くと、何を話せばいいのか「ネタ」が尽きてくるんですよね…。
しかも困ったことに(嬉しいことに?)、子どもたちは教育実習生の話の内容をよく覚えてくれているので、最終日に「◯◯の話が心に残っています」などと言われることもあります。
…手抜きはできませんねw
そこで、朝の会・ホームルームで使えるネタを15個集めました。
- 今朝のニュースを見た感想
- 偉人の話
- 名言・座右の銘紹介
- 学生時代の話
- 学生時代の友達との今の関係
- 大学生の一日
- 名前の話
- 勉強のやり方に役立つ話
- 世界の面白い文化
- 今年の目標発表と今の進捗状況
- 健康ワンポイントアドバイス
- 自分の専門教科を生かした雑学
- 好きな本の紹介
- 今日は何の日?
- 特技披露
それぞれ2〜3分ほどで喋れる「文例」付きで、詳しくまとめました。
教育実習のホームルーム・朝の会ネタが気になる方はこちら↓
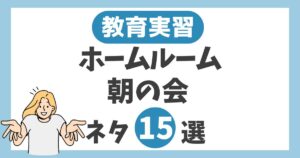
【養育実習】メモ・実習日誌ノウハウ
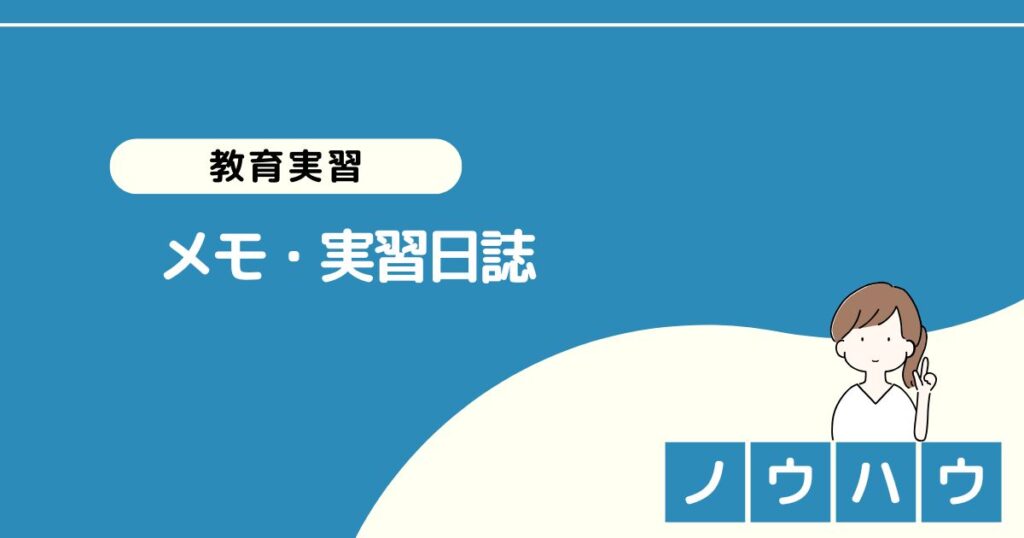
教育実習中、毎日書かなければならないものがあります。
それは「メモ」と「実習日誌」。
メモの適切な書き方を知っていれば、深い学びができるようになり、
実習日誌の書き方を知っていれば、素早く書き終えてその後の時間を効率よく過ごせるようになります。
ここでは「メモ術」と「実習日誌の書き方」を見ていきましょう。
ノウハウ⑥:授業見学メモ術
授業見学のときのメモには、3つのポイントと3つのメモ術があります。
基本の3つのポイントは、
- 授業の流れをメモする
→授業の「導入」「展開」「終末」の流れでメモする - 教師の手立てをメモする
→発問・板書・ノート指導・教材教具などの手立てをメモする - 子どもの様子をメモする
→反応・表情を元に理解度を測る・発言を元に児童の思考に触れる
まずは、この3つのポイントでメモを取るようにしましょう。
(最初は教師の手立てを追うので精一杯だと思います)
そして慣れてきたら、3つのポイントに加えて、以下の3つのメモ術をプラスしていきましょう。
- 自分の考え・疑問をメモに付け足す
- 分析的に見る
- アクションプランを書く
この3つのメモ術を加えることで、見学した授業の良い部分を、あなたの授業実践に活かせるようになります。
詳しいメモの取り方や生かし方については、教育実習のメモ術3選の記事をご覧ください↓

ノウハウ⑦:教育実習日誌の書き方
毎日、学んだこと・実践したことについてびっしり書かなければならない「教育実習日誌」。
実は、教育実習日誌は「授業見学・観察の日」と「授業実践の日」で書き方が異なります。
授業見学・観察の日
- 今日の目標
→その日に特に注目したい点や学びたいことを具体的に書きます - 実習・活動内容
→見学した授業の概要や、その他の活動内容を時系列で記録します - 気づき、学びになったこと
→指導教員の工夫や効果的だった指導方法などを記録します - 感想・考察
→観察した内容について、なぜ効果的だったのか、どのような意図があったのかを考察します - 取り入れたいこと・代替案・アクションプラン
→自分が授業を行うときに活用したい点を具体的に記録します
授業実践の日
- 今日の目標
→その日の授業で特に意識したい点を具体的に書きます - 実習・活動内容
→実施した授業の流れや、その他の活動内容を時系列で記録します - 上手くいったこと・上手くいかなかったこと
→授業での成功点と課題点を具体的に記録します - 感想・考察
→なぜ上手くいった/いかなかったのか、その要因を分析します - 自己反省・改善目標・アクションプラン
→次回の授業に向けた具体的な改善点を記録します
それぞれの書き方をしっかり抑えておけば、毎日「効率よく」「能率よく」日誌を書けるようになります。
教育実習日誌の具体的な書き方・文例・その他のテクニックについて詳しく知りたい方は、
教育実習日誌の書き方記事をご覧ください↓
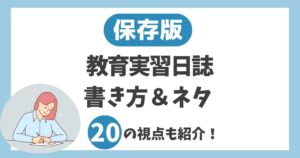
【教育実習】授業づくり・研究授業ノウハウ
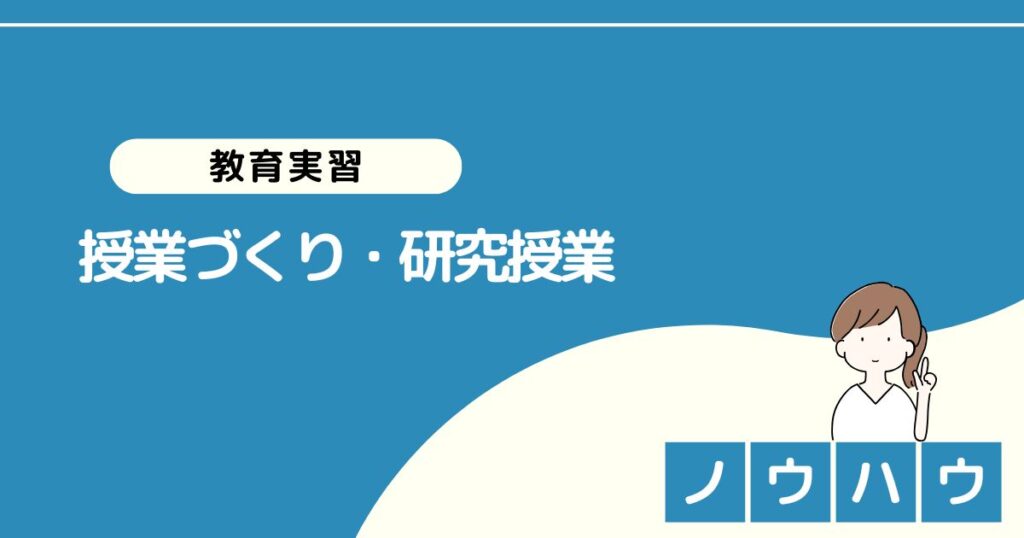
教育実習の一番の山場といえば「授業」。
ここでは、教育実習の授業を支える指導案と研究授業でのノウハウを紹介します。
ノウハウ⑧:指導案づくりのノウハウ
教育実習でもっとも大変な作業の1つが「指導案づくり」です。
教育実習の指導案づくりを成功させるためには、5つのポイントがあります。
- 基本をしっかり抑える
- いきなり完成を目指さない
- 指導案「だけ」に時間を使わない
- 書籍から学ぶ
- 締切に間に合わせる
5つのポイントをここで詳しく紹介すると、終わらなくなってしまうので…、
教育実習の指導案づくりを成功させる5つのポイントを詳しく知りたい方は、こちらを要チェックです↓
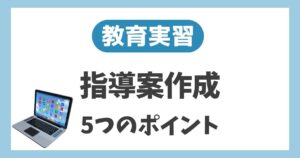
ノウハウ⑨:研究授業のノウハウ
教育実習で絶対に失敗したくない授業。それが「研究授業(査定授業)」。
研究授業では、やってはいけない5つのことがあります。
- 指導案をちゃんと作らずに授業をする
- 大学の先生に研究授業のことを伝えていない
- 模擬授業をせずに本番に臨む
- 協議会のことを考えていない
- お世話になった先生方に感謝を伝えていない
つまり、この5つのことを避ければ、研究授業の失敗を避けられるようになります。
研究授業の詳しいノウハウについては、教育実習の研究授業でやってはいけない「5つの失敗行動」の記事で紹介しているのですが、
- 失敗しない指導案の作り方
- 指導案の配り方
- 時間配分のやり方
- 本番に失敗しない板書計画の作り方
- 本番に頭が真っ白になっても大丈夫な発問計画の作り方
- 授業セットの作り方
- 協議会での自評の述べ方
など、教育実習生に(現役の先生でも)役立つノウハウてんこ盛りで紹介しています。
ぜひチェックしてくださいね↓
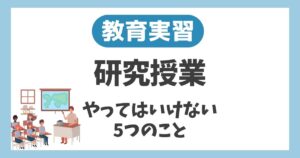
【教育実習】児童生徒へのプレゼントノウハウ
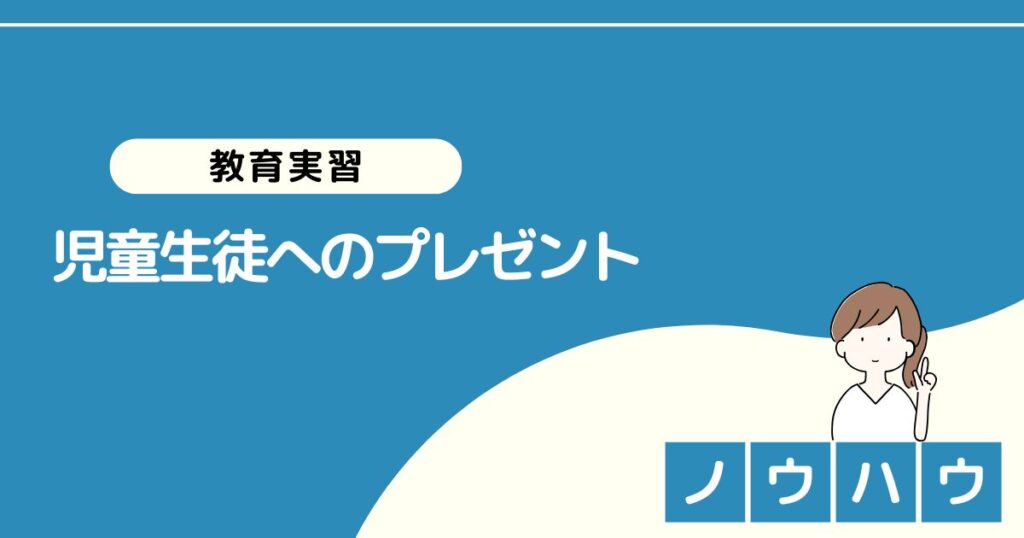
教育実習が終盤に差し掛かると、児童生徒へのプレゼントが脳裏にちらつき始めるのではないでしょうか。
児童生徒へのプレゼントは、必須ではありませんが多くの教育実習生が作成して渡しているのも事実です。
ここでは、教育実習での児童生徒へのプレゼントの「要」「不要」についての考え方や、プレゼントアイデア・具体的な文例について紹介します。
ノウハウ⑩:児童生徒へのプレゼントアイデア10
教育実習の最後に、クラスの児童生徒にあげるプレゼント。
まずは、大前提の話をさせていただくと、教育実習では児童生徒へのプレゼントは基本不要です。
教育実習の本務は「授業づくり」「受賞実践」「児童生徒との関わり方」を学ぶこと。
児童生徒へのプレゼントづくりによって、授業づくりの時間が圧迫されるようなら、プレゼント作成はやめるべきです。
あくまでも、時間に余裕がある場合に、「お金をかけずにできる」「手作りで気持ちがこもったもの」を渡すようにしましょう。
教育実習で児童生徒に渡すおすすめプレゼントとしては、以下のようなものがあります。
- 個別プレゼント
- しおり
- 名前キーホルダー
- 折り紙
- メッセージカード
- 手紙(個別)
- 漢字のプレゼント
- イラスト
- クラスの1つのプレゼント
- 手紙
- 歌
- 日めくりカレンダー
それぞれのイメージ画像や、作り方については教育実習での児童生徒へのプレゼント10選に詳しくまとめています。
プレゼントで悩んでいるならこちらをチェック↓
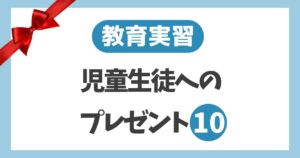
ノウハウ⑪:児童生徒への手紙・メッセージカード例文30
教育実習最終日、プレゼントをあげない場合でも、クラスの児童生徒に「手紙」を読もうと思っている人は多いのではないでしょうか。
数週間、共に学び、共に成長した子どもたちへの手紙。
感謝の気持や激励の言葉をしっかり伝えたいものですよね。
手紙を書くときには、文例を参考にしながら自分の言葉を紡いでいくことで、相手に伝わる文章を作れるようになります。
教育実習での児童生徒への手紙・メッセージカードの例文20では、小学校・中学校・高校別に手紙文例を準備しています。
手紙の言葉を考える時にお使いください↓
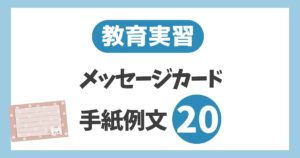
【教育実習】実習が大変・挫折しそうなときの考え方
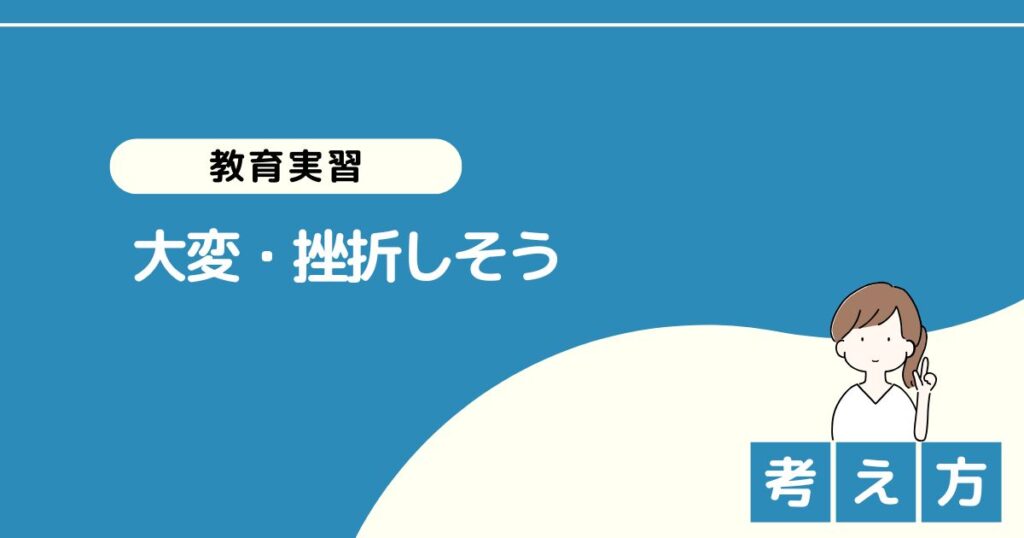
教育実習をしていると、途中で「きつい…やめたい…」と思う瞬間が来るかもしれません。
そのようなとき、どのように考えるのがよいのでしょうか。
3つのケースについて、私なりの考え方をお伝えしておきます。
ノウハウ⑫:授業がボロボロだった…ときの行動
教育実習では、一生懸命考えた授業がまったく上手く行かず、ボロボロな授業をやってしまうことがあります。
(私も経験あります)
ボロボロな授業をやってしまった後は、かなり落ち込むことでしょう。
それでも教員を目指すのをあきらめたくないのであれば、「気持ちを切り替えて授業改善をする」という行動を起こすしかありません。
気持ちを切り替えて授業改善をする流れは、以下のとおりです。
- メンタルを整える
・「どんなベテランの先生も最初は授業が下手だった」と思うようにする
・ノートに気持ちを書きなぐって感情を整理する - 次の授業の改善をする
・指導教官からのフィードバックをもらう
・指示・説明の仕方を学ぶ - 実習後も授業改善を行う
・授業力に関わる本を読む
・研究授業を見に行く
・セミナーに参加する
それぞれの詳細については、教育実習の授業でボロボロだったときの行動2選にまとめました。
授業力を高めたい方はぜひ↓
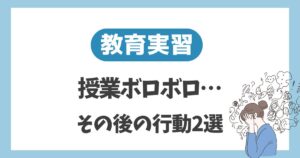
ノウハウ⑬:途中でリタイアしたいときの考え方
「教育実習がきつすぎる…途中で辞退したい。…けど」
と、あまりの大変さからリタイアしたいと感じることがあるかもしれません。
ただ、教育実習を途中で辞退してしまうと、将来のキャリアに大きく影響するので、慎重に考えなければなりません。
辞退したいと思ったときには、以下の2つの道についてよく考えてから行動に移すようにしましょう。
- 辞退せずに頑張ることで、教員の道が拓ける未来
(ただし、終了まで苦しみが続く) - 辞退して教員以外の新しいキャリアを見つける未来
(すぐに心身を休められる・自分の適性に合った職業が見つかるかも)
それぞれの道についてじっくり考えたい場合は、教育実習を途中で辞退・リタイアしたらどうなる?の記事をご覧ください↓
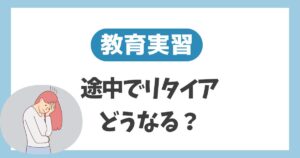
ノウハウ⑭:「教員に向いていない」と気づいたときの考え方
教育自習を通して「自分は教員に向いていない」と感じることがあるかもしれません。
教員に向いていないと気づいたときの選択肢は2つ。
- あきらめずに教員の道へ進む
- 新しい道を探す
ただし、気をつけてほしいのは、必ずしも「教員に向いていないと感じる=教員の道をあきらめたほうがいい」というわけではないということ。
あなたが、何に対して「向いていない」と感じたのかを言語化することが大切です。
教育実習で自分は教員に向いていないかもと感じた方は、こちらの記事をチェックしてくださいね↓
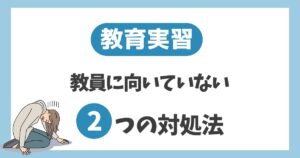
【教育実習】実習後のノウハウを確認する
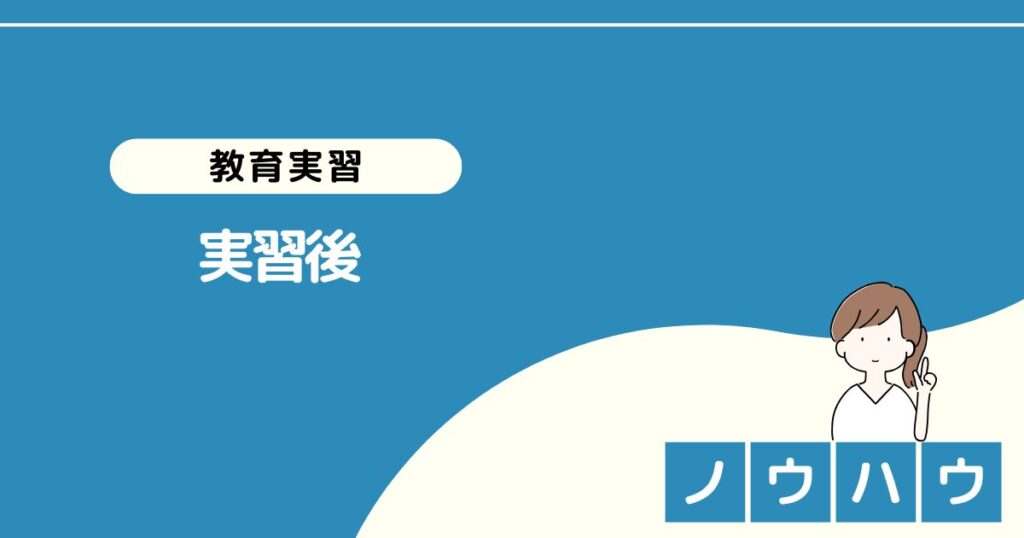
教育実習が無事に終わり、一安心…
と思いきや、まだすべきことが残っていますよ。
- 教育実習の感想・レポート・学んだことの書き方
- お礼状の書き方
- 教育実習打ち上げ・飲み会のマナー
などが気になる方は、教育実習後にすることまとめ記事で紹介しています↓