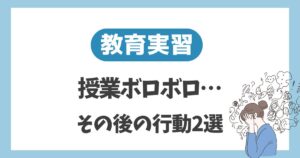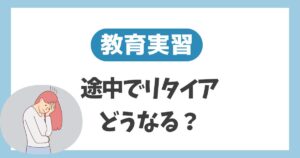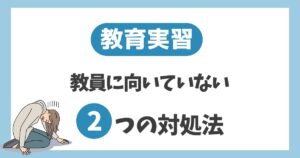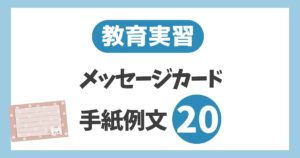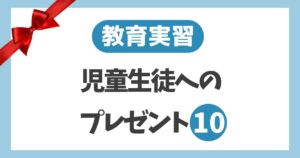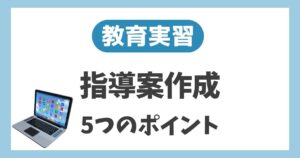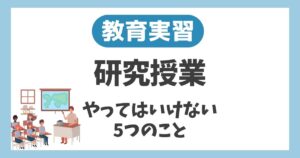教育実習のホームルーム・朝の会ネタ15選|今日すぐに使える!
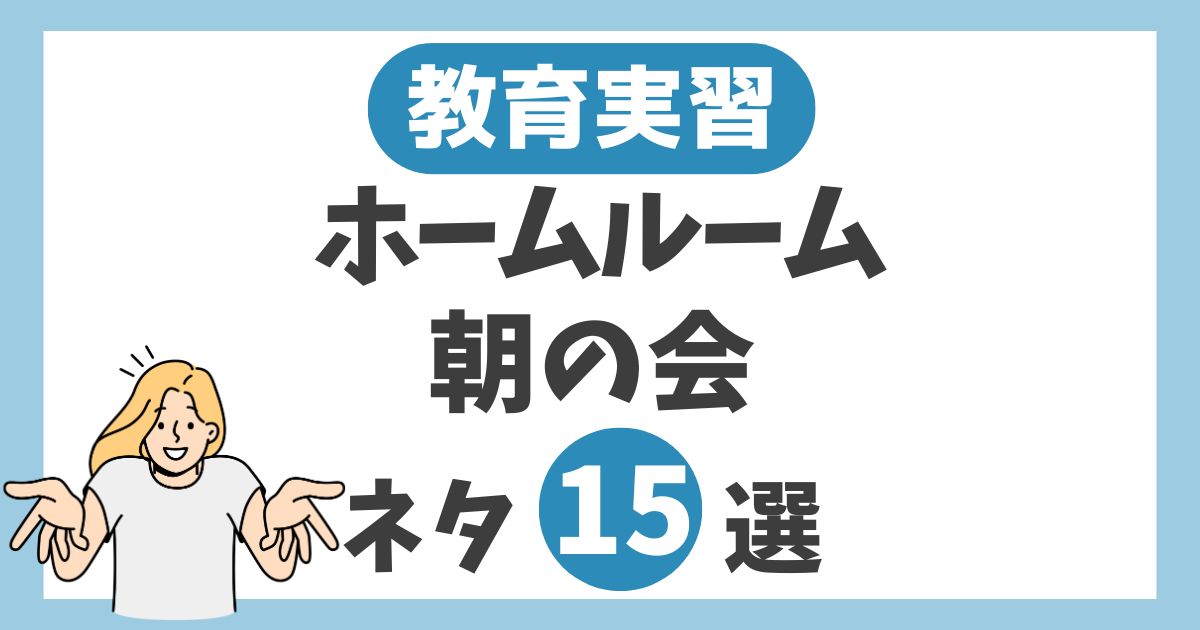
「教育実習でホームルームや朝の会で話すネタが思いつかない!」
「生徒の心をつかむネタってどんなものがあるのかな?」
と思っている教育実習生の方も多いのではないでしょうか。
教育実習で定番なのが、ホームルームや朝の会にある「教育実習生の話」の時間。
どんな話をすれば児童生徒たちが興味を持ってくれるか、不安になりますよね。
この記事では、教育実習中のホームルームや朝の会で使えるネタを15選、具体的な話し方例も交えながら紹介します。
記事を読むことで、朝の会やホームルームのネタに困ることがなくなりますよ。
あわせて読みたい(タップで閉じる)
教育実習ホームルーム・朝の会ネタ①:今朝のニュースを見た感想

教育実習の朝の会・ホームルームで扱えるネタ1つ目は、今朝のニュースを見た感想です。
「今朝のニュース」を取り上げるよさとコツ
その日の朝のニュースを取り上げることは、
- 児童・生徒たちの社会への関心を高められる
- 時事問題について考えるきっかけを提供できる
といった点から効果的です。
ニュースを取り上げる際は、以下のポイントを抑えながら話題選びをしましょう。
- 生徒の年齢や発達段階に適した内容を選ぶ
- センシティブな話題は避ける
- できるだけポジティブな内容や建設的な話題を選ぶ
例えば、スポーツの話題や科学の発見、地域の出来事など、児童生徒たちが興味を持ちやすいニュースを選ぶのがおすすめ。
また、ニュースの内容をしゃべるだけでなく、「みなさんはどう思いますか?」といった問いかけを入れることで、児童生徒たちの考える力を養うこともできます。
今朝のニュース例文
例文(小学生向け)
今朝のニュースで、野球の大谷選手が試合で活躍している様子を見ました。なんと、ホームランを打った後にピッチャーとしても投げていたんです。一つのことだけでなく、いろんなことに挑戦する大谷選手。最初は難しいことも、毎日コツコツ練習すれば、できるようになるんですね。大谷選手も、今の活躍までたくさん練習を重ねてきたはずです。みんなも、今チャレンジしていることはありますか?「今こんなことに挑戦してるよ!」ということがあったら、今日の休み時間に、先生に教えに来てくださいね!
例文(中学生向け)
今朝のニュースで、私たちの地域の防災訓練の様子が取り上げられていました。特に印象的だったのは、中学生ボランティアの活躍です。実は去年の大雨の時、この地域の避難所で中学生たちが高齢者の方々の案内や物資の運搬を手伝い、とても助かったという声があったそうです。その経験を活かして、今回の訓練では中学生の役割が明確に組み込まれていました。私たち中学生も、いざという時に地域の力になれる存在なんですね。今週末も地域の防災訓練があります。皆さんも参加してみませんか?
例文(高校生向け)
みなさん、おはようございます。今朝のニュース見ました?日本の高校生が開発したアプリが、世界的なコンテストで優勝したんです。そのアプリは、お年寄りの方々の買い物をサポートするためのもので、画面が見やすく、音声での操作もできるという工夫がされているそうです。
このニュースを聞いて、皆さんはどう感じましたか?私は、「誰かの役に立つ」ということを形にするって素敵だなと感じました。高校生でもアイデア次第で、世界を変えることができる。世界を変える必要はないかもしれませんが、身近な人の役にたったり、友達の役に立つアイデアならすぐに思いついて実践できるかもしれません。みなさんも、日頃から「こんなものがあったらいいな」という視点で物事を見てみると、新しい発見があるかもしれませんよ。
教育実習ホームルーム・朝の会ネタ②:偉人の話

教育実習の朝の会・ホームルームで扱えるネタ2つ目は、偉人の話です。
「偉人の話」を取り上げるよさとコツ
歴史上の偉人の生き方や考え方を紹介すると、
- 生徒たちに夢や目標を持つことの大切さ
- 偉人が直面した困難や、それをどのように乗り越えたか
という内容を伝えられるのがいいですね。
偉人の話を取り上げる際は、以下のポイントを意識して選びましょう。
- 生徒の年齢や興味に合わせた偉人を選ぶ
- 現代にも通じる教訓がある話を選ぶ
- 具体的なエピソードを交えて話す
- 偉人の人間的な側面も含めて紹介する
偉人の話の例文
今日は『電話』を発明したグラハム・ベルの話をします。ベルは、お母さんが耳の不自由な方だったこともあり、音や声の研究に興味を持っていました。発明家になる前は、実は聾唖学校の先生をしていたんです。生徒さんとのコミュニケーションをもっと便利にしたい、その思いが電話の発明につながりました。最初は多くの人が『そんなの無理だよ』と言いましたが、ベルは諦めませんでした。みんなの身近にある電話も、誰かの『できたらいいな』という思いから生まれたんです。皆さんも、『できたらいいな』という思いを諦めずに挑戦してみてくださいね。
今日は、発明王と呼ばれたエジソンの面白いエピソードをお話しします。エジソンは小学生の時、実は勉強が苦手で学校の先生から『頭が悪い』と言われてしまいました。でもお母さんは『トーマスは賢い子よ』と信じ続けて、家で勉強を教えました。エジソンは大人になってから『僕が発明家になれたのは、母さんが僕を信じてくれたおかげだ』と言っています。そうそう、電球の発明の時は1000回以上も失敗したんです。でも彼は『1000回の失敗じゃない。電球を作る方法じゃない方法を1000個見つけたんだ』と言って、笑顔で実験を続けました。みんなも、何か失敗して悲しくなることがあるかもしれません。でも、その失敗も大切な経験なんですよ。
「他の偉人の話をもっと知りたい」という方は、こちらもチェックしてみて>>
教育実習ホームルーム・朝の会ネタ③:名言・座右の銘紹介
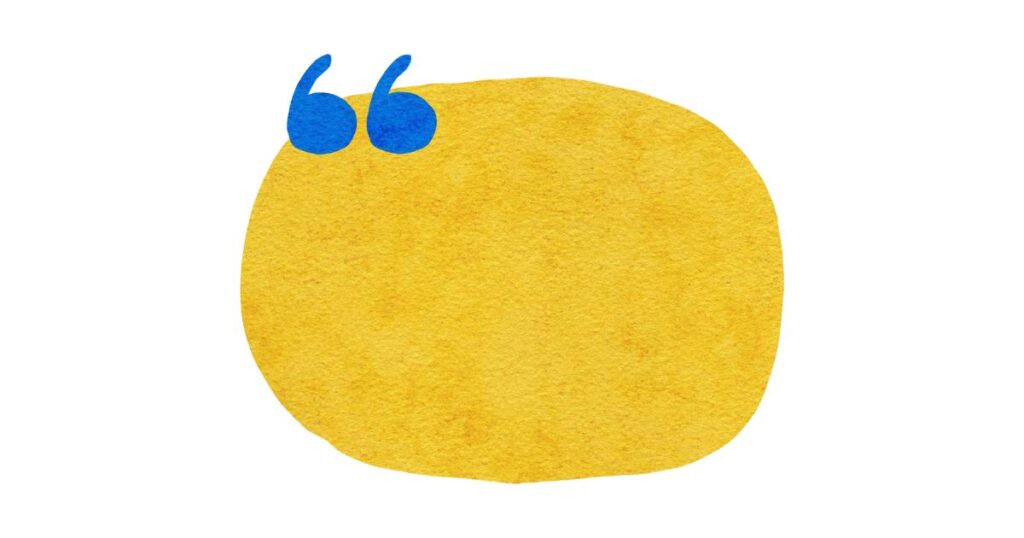
教育実習の朝の会・ホームルームで扱えるネタ3つ目は、名言・座右の銘の紹介です。
「名言・座右の銘」を取り上げるよさとコツ
名言や座右の銘を紹介することには、
- 児童生徒たちに新しい視点や考え方を提供できる
- 先生(あなた)の大切にしている価値観を伝えられる
という良さがあります。
名言・座右の銘の例文
例文
今日は『転んでもただでは起きるな』という言葉を紹介します。これは、失敗したり困ったりした時、そこから何か学びを得ようという意味です。実は昨日、休み時間に面白いことがありました。鉄棒の逆上がりの練習をしていた◯◯さん。最初は、何度も失敗して転んでしまったんです。でも、その度に『あ、今のは手の位置が違ったな』『今度は足の振りが足りなかったな』と、どんどんコツを見つけていきました。最後には、なんと初めて逆上がりができたんです!転んでしまっても、そこから学べることはたくさんあるのです。みんなも何か頑張っていることで、失敗することがあると思います。でも、『転んでもただでは起きるな』。失敗の中からコツを見つけて、成功できるようにがんばってくださいね。
今日は、野球選手のイチロー選手が大切にしていた『小さいことを重ねることが、とんでもないところへ行くただ一つの道』という言葉を紹介します。イチロー選手は、毎日必ずバットの素振りを1000回していたそうです。それに、練習の後は必ず使った道具を丁寧に手入れして、グローブの紐も自分で編み直していました。そうそう、ユニフォームのたたみ方にもこだわっていたんです。小さな積み重ねの力を信じていたんですね。みんなも、毎日コツコツ続けていることはありますか?宿題でも、お手伝いでも、小さなことの積み重ねが、きっと大きな力になりますよ。
今日は、戦国時代の武将・織田信長の『言われたことしかやらないのは雑兵だ』という言葉を紹介します。雑兵というのは、ただ言われた通りに戦う普通の兵士のことです。でも信長は、自分で考えて行動できる人を大切にしていました。誰かに『こうしなさい』と言われるのを待つのではなく、自分の頭で考えて行動する。そんな人たちを育てたおかげで、信長は強い軍団を作ることができたんです。みんなも、毎日の生活の中で『こうしたら良くなるかも』と考えることはありますか?『言われたことしかやらないのは雑兵だ』。自分で気づいて行動できると、きっと素晴らしいことが起きるはずですよ。
他の「名言・座右の銘」も知りたいという方は、こちらもチェックしてみて>>
教育実習ホームルーム・朝の会ネタ④:学生時代の話

教育実習の朝の会・ホームルームで扱えるネタ4つ目は、学生時代の話です。
「学生時代の話」を取り上げるよさとコツ
教育実習生が、自分の子どもの頃の話をすることには、
- 児童生徒たちとの距離を縮める
- 共感を得る
- 関心・関心を引く
という良さがあります。
自分の子どもの頃のエピソードを選ぶポイントとしては以下のとおりです。
- 現在の生徒たちが共感できる内容
- 教訓や学びがある経験
- 明るく前向きな内容
- 適度な失敗談を含める
ただし、自慢話に聞こえないよう注意が必要です。
むしろ、自分の失敗や苦労を笑い話として語ることで、生徒たちに「失敗は成長の糧」というメッセージを伝えることができますよ。
学生時代の話の例文
今日は、私の小学校4年生の時の話をします。給食が苦手で、特に苦手だったのが玉ねぎの入ったスープ。玉ねぎを避けながら飲むのに、いつも時間がかかっていました。ある日、担任の先生が『なぜ玉ねぎが苦手なの?』と聞いてくれて、『食感が気持ち悪いんです』と答えると、『じゃあ、今度は細かく刻んだ玉ねぎから挑戦してみたら?』とアドバイスをくれました。最初は半信半疑でしたが、少しずつ試してみると、案外平気だということに気づいたんです。今では玉ねぎ、むしろ好きな野菜の一つです。苦手なことも、小さな一歩から始めれば、きっと克服できる。そんなことを教えてくれた思い出です。
私が6年生の時の運動会の話をします。リレーの選手に選ばれたのですが、練習の時、何度も何度もバトンを落としてしまって。チームのみんなに申し訳なくて、もう走りたくないって思ったこともありました。でも、休み時間に同じチームの友達が『一緒に練習しよう』と声をかけてくれて。放課後も付き合ってくれて、バトンの受け渡しの練習を重ねました。本番では…実は最後の最後でまたバトンを落としてしまったんです。でも、チームのみんなが『次頑張ろう!』って声をかけてくれた。結果より大切なものがあるんだって、その時気づきました。今でも忘れられない思い出です。
高校2年の文化祭実行委員の思い出です。私、生まれて初めて大きな仕事を任されて。100人以上の前で企画案のプレゼンをすることになったんです。準備が不十分なまま臨んでしまい、質問攻めに遭って頭が真っ白に。その場で泣きそうになって、途中で席に戻ってしまいました。でも、委員長が『次は一緒に準備しよう』と声をかけてくれて。先輩たちと何度も打ち合わせを重ねて、2週間後に再チャレンジ。今度は質問にもなんとか答えられて、企画も通りました。大変でしたが、『準備をしっかりすること』『周りに助けを求めること』の大切さを学んだ経験です。
教育実習ホームルーム・朝の会ネタ⑤:学生時代の友達と今どのような関係を続けているか

教育実習の朝の会・ホームルームで扱えるネタ5つ目は、学生時代の友達と今どのような関係を続けているか、という話です。
「学生時代の友達との今の関係」を取り上げるよさとコツ
学生時代の友人関係が現在まで続いている話は、人間関係の大切さを伝える良い機会となります。
今、仲良くしている友達と、これからもずっとつながっていけると考えたら、学校での友達作りも楽しくなりますよね。
友人関係について話す際のポイントは、
- 良好な関係を維持するためのコツ
- 思い出の共有の大切さ
- 互いに支え合うことの意義
- 年月を経ても変わらない友情の価値
例えば、定期的な同窓会の様子や、お互いの人生の節目で支え合った経験など、具体的なエピソードを交えながら話すことで、生徒たちに友人関係の深さや継続することの意味を伝えることができます。
学生時代の友達との今の関係の例文
例文(小学生向け)
みなさんは今、休み時間に一緒に遊んだり、給食を食べたりする友達がいますよね。実は私にも、小学校の時からずっと仲良しの友達がいるんです。運動会の練習で失敗ばかりしていた時、『大丈夫、一緒に練習しよう』と声をかけてくれた友達です。それから15年たった今でも、誕生日には必ずメッセージを送り合っています。先日は、その友達の結婚式に参加して、小学校の思い出話で盛り上がりました。友達と一緒に頑張った思い出は、大人になっても宝物のようです。みなさんも、今一緒にいる友達と楽しい思い出をたくさん作ってくださいね。
例文(中学生向け)
部活動の仲間との関係は、とても特別なものです。私の場合、中学校のバスケ部の仲間とは今でも月に1回、必ず集まっています。部活を引退した3年生の時、最後の大会で負けて一緒に悔し涙を流した仲間です。今は、それぞれ違う仕事についていますが、悩みがある時は LINE で相談し合い、お互いの頑張りを応援しています。部活での厳しい練習も、試合での緊張も、全部乗り越えてきた仲間だからこそ、何でも話せる存在なんです。大切な友達関係を続けるコツは、お互いの生活や考え方を尊重しながら、定期的に連絡を取り合うことだと思います。
例文(高校生向け)
高校時代の友人関係は、人生の転機で大きな支えとなります。私の場合、進路に悩んでいた時期に、放課後によく図書館で一緒に勉強していた友人たちと、今でも密に連絡を取り合っています。それぞれ違う大学に進学していますが、月1回のオンライン飲み会が恒例になっています。高校時代に培った『一緒に考え、励まし合う』という関係が、3年経った今も変わらず続いているんです。友情を長く保つには、お互いの成長を喜び合える関係性が大切だと実感しています。皆さんにとっての高校生活も、将来にわたる大切な絆を育む機会になるはずです。
教育実習ホームルーム・朝の会ネタ⑥:大学生の一日

教育実習の朝の会・ホームルームで扱えるネタ6つ目は、「大学生の一日」です。
「大学生の一日」を取り上げるよさとコツ
大学受験を控えた高校生や、キャリアについて漠然としている中学生にとって、現役大学生の日常生活について語ることは、将来の具体的なイメージづくりに役立ちます
大学生活を紹介するときには、以下のポイントに気をつけるとよいでしょう。
- 時間割の組み方と自己管理
- サークル活動や課外活動の様子
- アルバイトとの両立
- 勉強方法の違い
ただし、大学生活を美化しすぎないよう注意が必要です。
自由な時間が増える分、責任も増えることをしっかりと伝えましょう。
大学生の一日の例文
例文(小学生向け)
大学生になると、みなさんと違って、時間割を自分で決めることができます。例えば、私は火曜日と木曜日の午前中に授業をたくさん入れて、水曜日の午後は空けて、好きな絵画サークルの活動に参加しています。でも、自分で決められる分、授業に遅刻しないように気をつけたり、宿題の提出日を忘れないように手帳でしっかり管理したりする必要があります。放課後や休みの日には、本屋さんでアルバイトをして、お小遣いを稼いでいます。お客様に本の場所を案内するのは、図書委員の活動みたいで楽しいですよ。みなさんも将来、自分の時間を上手に使える大人になってくださいね。
例文(中学生向け)
皆さんは『大学生の1日ってどんな感じかな?』と思ったことはありますか?中学校と大きく違うのは、授業の時間割を自分で決められることです。私の場合、火曜日はこんな感じです。
朝9時から『教育心理学』の授業を受けて、その後11時から『英語』。昼休みを挟んで午後1時から『体育』があります。授業が終わる3時からは、バドミントンサークルの練習に参加。夕方6時からは学習塾で小学生に勉強を教えるアルバイトをしています。
他の曜日は違う時間割で、月曜日の午後は全部空いているので、図書館で課題をしたり、友達とカフェで勉強したりします。自分の好きな時間に好きなことができる分、授業に遅刻しないように気をつけたり、課題の提出日を忘れないように手帳にメモしたりと、自己管理が大切になります。でも、自分の興味のある授業を選んで、空き時間にサークルやアルバイトを楽しめるのが、大学生活の魅力だと思います。
例文(高校生向け)
私の大学生活を具体的にお話ししますね。ある平日の1日のスケジュールはこんな感じです。
8:00 起床、支度
9:00-10:30 教育原理の授業
10:40-12:10 英語コミュニケーション
12:10-13:00 友達と学食で昼食
13:00-14:30 教職科目(生徒指導論)
15:00-17:00 教育ボランティアサークル
18:00-21:00 塾講師のアルバイト
22:00 帰宅、課題や予習
高校と違って、授業の予習復習は自分次第です。先生から『この範囲をやってきなさい』と細かく指示されることは少なく、自分で参考書を探して読んだり、友達と一緒に勉強したりします。テスト前は図書館に集まって勉強会をすることもあります。
空き時間は自由に使えますが、その分、自己管理も必要です。例えば、来週提出のレポート、サークルの活動、アルバイトのシフトなど、すべて自分で調整しないといけません。最初は大変でしたが、手帳を使って予定を管理する習慣がついてきました。
高校生の時と比べると、自分の意志で選択できることが増えます。その分、責任も出てきますが、自分の興味に合わせて授業を選び、サークルやアルバイトで新しい経験ができるのは、とても楽しいですよ。
教育実習ホームルーム・朝の会ネタ⑦:名前の話

教育実習の朝の会・ホームルームで扱えるネタ7つ目は、「名前の話」です。
「名前の話」を取り上げるよさとコツ
教育実習では、児童生徒の名前を全員覚える必要があるので、「名前」にふれる機会が多いです。
そのことを切り口に、「名前」に関わるあたたかいエピソードを話のがおすすめです。
以下の例文を元に、「名前」の話をしてみてくださいね。
名前の話の例文
親からはじめてもらったプレゼント、覚えていますか?
実は、みなさんは、生まれてすぐに親からプレゼントを貰っているのです。
そのプレゼントとは『名前』です。
私たちの名前には、たくさんの願いが込められています。美しい響きだったり、呼びやすい音だったり、兄弟や家族とのつながりを感じられるものだったり。漢字の持つ意味を大切に選んでくれたり、画数にこだわって考えてくれたり。きっとお家の人は、みなさん一人一人の名前を決めるとき、幸せな気持ちでいっぱいだったことでしょう。
この3日間で、みなさんの名前を覚えましたが、ほんと素敵な名前ばかりだなぁと感じています。
私たちの『名前』は、はじめてもらった親からのかけがえのないプレゼントです。『なぜこの名前にしたの?』と、両親に聞いてみると、素敵な話が聞けるかもしれませんね。みなさんの名前には、両親からの大切な思いが込められています。その名前を、大切にしていってくださいね。
教育実習ホームルーム・朝の会ネタ⑧:勉強のやり方に役立つ話
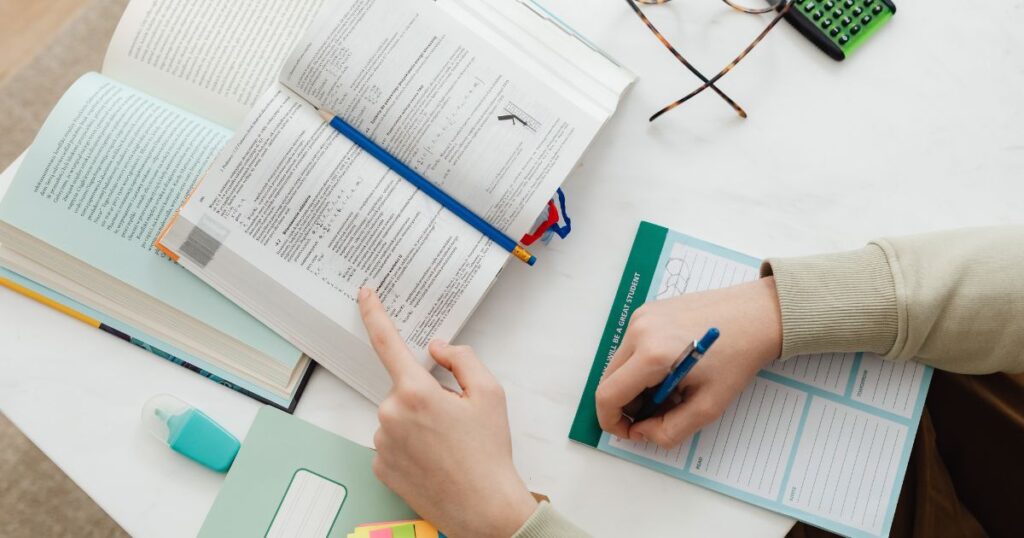
教育実習の朝の会・ホームルームで扱えるネタ8つ目は、「勉強のやり方に役立つ話」です。
「勉強のやり方に役立つ話」を取り上げるよさとコツ
勉強のやり方に役立つ話を取り上げることで、児童生徒の学習のやり方によい影響を与えることができます。
学校では「教科学習」を教わる機会は多いですが、意外と「勉強のやり方」「学び方」について知る機会は少ないものです。
そのため、おすすめの勉強方法や時間管理法などを子どもたちに伝えると、ありがたがられますよ。
勉強のやり方に役立つ話の例文
例文(小学生向け)
みなさんは、『お気に入りノート』を知っていますか?私が小学生の時に使っていた、勉強が楽しくなる方法です。
このノートには、授業で『わあ、すごい!』『へぇ、そうなんだ!』と思ったことを、好きな色のペンで書きます。例えば、理科の授業で習った『メダカは目を閉じずに眠る』という面白い発見。社会の授業で知った『世界一高い山、エベレストは今でも少しずつ高くなっている』という不思議な事実。算数で習った『九九は指を使って計算できる』というびっくりする方法などなど。
お気に入りノートを作ると、3つの良いことがあります。 1つ目は、楽しいことを書くから、自然と授業を集中して聞けるようになります。 2つ目は、好きな色で書くから、後で見返すのが楽しくなります。 3つ目は、友達と「へぇ、それ知らなかった!」って見せ合えるから、お勉強が楽しくなります。
みなさんも、明日からお気に入りノートを作ってみませんか?きっと、勉強の時間が楽しみになりますよ。
例文(中学生向け)
テスト勉強って、どうやって準備していますか?今日は、私が中学生の時に見つけた『3色まとめノート法』を紹介します。
この方法は、教科書やノートの内容を、3色のペンを使って整理していきます。
黒は「基本的な事実や公式」。赤は「重要な用語や覚えるべきポイント」。青は「具体例や自分なりの説明」
ノートを作るコツは、『自分の言葉で書く』ことです。教科書をそのまま写すのではなく、『あぁ、そういうことか!』と分かった時の自分の理解を書きます。特に青で書く具体例は、自分が『なるほど!』と思った例を書くと良いんです。
まとめノートを作る時間は、その日の授業の内容を30分以内でまとめるのがおすすめです。一度にたくさんやろうとせず、毎日少しずつ。そうすると、テスト前にノートを見返した時、すぐに思い出せて復習がラクになりますよ。
このノートは、最初は時間がかかるかもしれません。でも、続けていくうちに要点をつかむ力が身につき、だんだん早くできるようになります。何より、自分だけの分かりやすいノートができあがっていくのが楽しいんです。ぜひ、次の定期テストに向けて挑戦してみてください。
例文(高校生向け)
今日は、脳科学の研究から分かった効果的な勉強法についてお話しします。特に、集中力と記憶力を最大限に活用する『ポモドーロ・テクニック』という方法を紹介します。
ポモドーロ・テクニックというのは、25分の集中作業と5分の休憩を1セットとする時間管理法です。なぜ25分かというと、人間の集中力には波があり、20〜30分でいったん低下することが分かっているからです。
具体的なやり方は、
①最初に、その日の目標を明確に設定します。例えば、「古典の文法問題を10問解く」「英単語を30個覚える」などです。
②25分のタイマーをセット この間は、スマートフォンを別室に置くなど、気が散る要素を排除します
③タイマーがなったら、5分の休憩で気分転換します。このときはSNSなどは避け、軽い運動や深呼吸がおすすめです
④これを4セット繰り返します。終わったら、15〜30分の長めの休憩をとって、また①から始めます
25分という時間は、集中力を使い切る前に休憩を取れるので、疲労が少なく、長時間の学習も可能になります。
ぜひ、来週の定期テストや受験勉強に取り入れてみてください。
教育実習ホームルーム・朝の会ネタ⑨:世界の面白い文化

教育実習の朝の会・ホームルームで扱えるネタ9つ目は、「世界の面白い文化」です。
「世界の面白い文化」を取り上げるよさとコツ
世界の様々な文化や習慣を紹介することには、
- 児童生徒たちの視野を広げる
- 多様性への理解を深める
- 日本との違いや共通点を知って文化理解を促進できる
などのよさがあります。
外国語の教員免許を取りたい方や、海外旅行の経験がある方は、ぜひチャレンジしてほしい話題です。
「世界の面白い文化」の例文
例文(小学生向け)
みなさんは、イギリスに『おやつの時間』が決まっているって知っていますか?私が留学していた時、ホストファミリーのお家では、毎日午後3時になると『はい、ティータイムよ!』と声がかかりました。
紅茶とスコーンというお菓子を食べる大切な時間です。面白いことに、大人も子どもも、仕事や勉強を中断して、家族みんなでテーブルを囲みます。スコーンにはジャムとクリームをたっぷり塗って、紅茶に砂糖とミルクを入れて、その日にあった出来事を話します。
最初は『なんで毎日同じ時間におやつ?』って不思議に思いました。でも、家族で集まってお話しする時間が毎日あるって、とても素敵なことだなって感じました。日本のお茶の時間とは少し違う、イギリスならではの温かい習慣です。
例文(中学生向け)
私が1年前、タイに2週間ホームステイした時の話をします。最初の数日は、とても戸惑うことがありました。それは、タイの人々の『時間感覚』です。
例えば、夕食の約束時間が6時だとします。日本なら5分前に着くように急ぐところですが、タイの友達は7時に現れても全く気にしません。『マイペンライ』という言葉があって、『気にしないで、大丈夫』という意味です。
最初は『約束の時間を守らないなんて…』と思いましたが、タイの人々は『人と会えること』を『時間ぴったり』より大切にしているんです。急がず、ゆっくり、でも心を込めて。この考え方に触れて、時間を守ることは大切だけど、もっと大切なことがあるのかもしれないって考えるようになりました。
例文(高校生向け)
フランスでの1ヶ月の交換留学で、私の『食事』に対する考え方が大きく変わりました。フランスの家庭では、平日の夕食でも最低1時間、休日なら2〜3時間かけて食事をします。
驚いたのは、その過ごし方です。前菜、メイン、チーズ、デザートと、少しずつ品数を重ねながら、その合間で様々な話題について会話を楽しみます。政治、芸術、学校のこと、将来の夢…。食事の時間は、単に『食べる』ためだけでなく、家族で意見を交わし、お互いを理解し合う大切な時間なんです。
特に印象的だったのは、スマートフォンの扱い方。食事中は完全にカバンの中にしまい、テレビも消します。『人と向き合う時間』を何よりも大切にする。この習慣は、今の私の生活にも大きな影響を与えています。
教育実習ホームルーム・朝の会ネタ⑩:今年の目標発表と、今の進捗状況
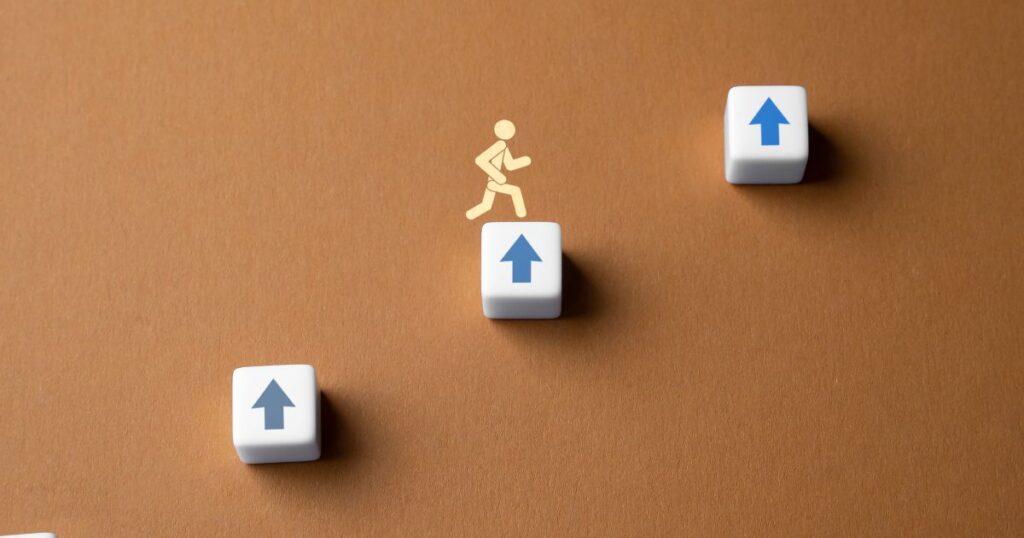
教育実習の朝の会・ホームルームで扱えるネタ10個目は、「今年の目標発表と、今の進捗状況」です。
「今年の目標と今の進捗状況」を取り上げるよさとコツ
自身の目標とその進捗状況を共有することには、
- 児童生徒たちに目標設定の重要性
- 目標達成に向けた計画の立て方
などを伝えられるよさがあります。
実際の経験に基づいた話をすることで、生徒たちに目標達成のリアルな過程を示すことができます。
今年の目標と今の進捗状況の例文
今年の私の目標は『フルマラソンを完走すること』です。42.195キロメートルも走るなんて、最初は無理かもしれないと思いました。でも『少しずつ頑張ろう』と決めて、取り組んでいます。
4月から今までを振り返ると、まず3キロ走れるようになって、それから5キロ、10キロと少しずつ距離を伸ばしてきました。最初は3キロでもバテバテだったのに、今は20キロまで走れるようになりました!
でも、まだフルマラソンの半分くらいです。だから、毎週土曜日の朝は必ずランニングの練習をして、少しずつ距離を伸ばしています。走る前には準備体操をしっかりして、水分もこまめに取るように気をつけています。
目標に向かって頑張る時は、『今日はここまで!』って決めて、できたらシールを貼ったり、カレンダーに記録したりすると楽しいですよ。みなさんも、自分の目標に向かって、一歩ずつ進んでいってくださいね。
私の今年の目標は『分かりやすい授業ができる先生になる』ことです。そのために3つの小さな目標を立てました。
1つ目は、声の大きさと話すスピードを適切にすること。 2つ目は、黒板の字を丁寧に書くこと。 3つ目は、生徒のみなさんの反応を見ながら説明すること。
今の進み具合を話すと、声の大きさは少しずつ良くなってきました。最初は緊張して早口になっていましたが、今は意識して落ち着いて話せるようになってきています。黒板の字は…正直まだまだです。放課後に練習していますが、もっと上手になりたいと思います。
目標を達成するのに大切なのは、自分の課題に正直に向き合うことです。できていることとできていないことを、はっきりさせる。そうすれば、次に何をすべきかが見えてきます。みなさんも、自分の目標への進み具合を時々チェックしてみてくださいね。
教育実習ホームルーム・朝の会ネタ⑪:健康ワンポイントアドバイス

教育実習の朝の会・ホームルームで扱えるネタ11個目は、「健康ワンポイントアドバイス」です。
「健康ワンポイントアドバイス」を取り上げるよさとコツ
健康のワンポイントアドバイスには、
- 児童生徒たちの日常生活に直接役立つ
- テスト期間や行事など、時期に合わせたアドバイスが可能
などのよさがあります。
健康ワンポイントアドバイスをするときには、「科学的根拠のある情報」「実践しやすもの」を取り入れるのが良いでしょう。
例えば、手洗いうがいの重要性や、適切な睡眠時間の確保方法など、日常生活に即した内容を選びましょう。
健康ワンポイントアドバイスの例文
例文(小学生向け)
みなさん、手洗いはしっかりできていますか?
実は私、大学で『手の中の細菌』について実験したことがあるんです。
ちゃんと手を洗った後は、細菌がほとんどいなくなっていたんです!でも、ただ水で流しただけの手には、まだたくさんの細菌が残っていました。
石鹸を使ってしっかり手を洗うことで、目に見えない細菌やウイルスを退治できます。
給食の前、外遊びの後、トイレの後には、必ず手を洗うようにしましょうね!
例文(中学生向け)
テスト期間、『夜更かしして勉強しなきゃ』と思っていませんか?
実は、夜更かし勉強より、『良質な睡眠』の方が成績アップには効果的なんです。
人間の脳は、睡眠中に『その日学んだこと』を整理して記憶に定着させます。特に夜10時から深夜2時までの睡眠が大切で、この時間帯にしっかり眠ることで、記憶力や集中力が高まることが研究で分かっています。
私のおすすめは『逆算式睡眠計画』です。
・起きる時間から逆算して8時間前には布団に入る
・寝る1時間前にはスマートフォンを見るのを止める
・寝る30分前に少し窓を開けて空気を入れ替える
・机に向かう時は明るい電気をつけ、横になって勉強しない
これを実践すると、朝スッキリ起きられて、テスト中も頭がクリアになります。テスト期間こそ、睡眠時間は削らないようにしましょう。
例文(高校生向け)
皆さんは『脳に良い食事』について考えたことはありますか
?実は、勉強や部活動のパフォーマンスは、食事と水分摂取で大きく変わってきます。
特に重要なのは『ブドウ糖』です。脳が使うエネルギーの約20%がブドウ糖で、これが不足すると集中力が急激に低下します。でも、お菓子など単純な糖分の摂取は、一時的な効果しかありません。
代わりに意識してほしいのが『複合炭水化物』です。玄米やパン、パスタなどに含まれる複合炭水化物は、ゆっくりとブドウ糖に分解されて、長時間安定したエネルギーを供給してくれます。
効果的な食事のポイントは、
・朝食は必ず摂る(パンや米、シリアルなどの炭水化物を含むもの)
・昼食後の眠気対策には、食事の量を適度に
・間食は果物やナッツ類を選ぶ
・水分は1日1.5リットルを目安に、こまめに取る
特に水分補給は重要です。2%の脱水で、計算力が10%以上低下するというデータもあります。教室に飲み物を持参して、1時間に1回は水分を取るようにしましょう。
これから受験期に入る人は特に、『食事=脳のエネルギー源』という意識を持って、バランスの良い食生活を心がけてください。
教育実習ホームルーム・朝の会ネタ⑫:自分の専門教科を生かした雑学

教育実習の朝の会・ホームルームで扱えるネタ12個目は、「自分の専門教科を生かした雑学」です。
「自分の専門教科を生かした雑学」を取り上げるよさとコツ
自分が専門的に学んでいることであれば、雑学の1つや2つは持っていることでしょう。
それらの話をすることで、子どもたちはあなたの専門教科についての興味を持つことができます。
「大学生ってどんなことを学んでいるんだろう?」と興味を持っている子も多いと思うので、ぜひ自分の専門教科の雑学を話してあげてみてくださいね。
自分の専門教科を生かした雑学の例文
例文(小学生向け)
みなさんは『脳は運動が大好き』って知っていますか?
私が大学で勉強して、すごく驚いた発見をお話しします。
実は、外で体を動かして遊んだ後の方が、計算や漢字が覚えやすくなるんです。これは、体を動かすことで脳が『やる気スイッチ』をONにするからなんです。
休み時間に外で遊ぶと、次の授業でより集中できるのはこのためなんですよ。
面白いことに、指や手を動かすことも脳にとってはとても大切な運動です。だから、習字を書いたり、図工で何かを作ったりすることも、実は脳のトレーニングになっているんです。
みなさんの脳は、毎日新しいことを学ぼうとワクワクしています。だから、少し難しいことにチャレンジする時は『よし、脳が喜んでるぞ!』って思ってくださいね。
例文(中学生向け)
今日は、私が大学の『発達心理学』の授業で学んだ『記憶の不思議』についてお話しします。
人の記憶には『短期記憶』と『長期記憶』があります。面白いことに、新しい情報は最初の10分で約40%が忘れられてしまうんです。でも、その時に『自分の言葉で説明してみる』『図や表で整理する』という作業をすると、記憶の定着率が3倍以上高まることが分かっています。
例えば、数学の新しい公式を習った時。ただ暗記しようとするより、『なぜこの公式になるのか』を友達に説明してみる方が、実は記憶に残りやすいんです。これは『教えることで学ぶ』効果と呼ばれています。
私もこの知識を使って、授業で習ったことをその日のうちにノートに『自分の言葉で』まとめる習慣をつけています。みなさんも、ぜひ試してみてください。
例文(高校生向け)
今日は、教育心理学で注目されている『望ましい困難度』という考え方を紹介します。
私たちの脳は、『ちょっと難しい』と感じる課題に取り組む時が最も効率よく学習できます。具体的には、正解率が約80%くらいの難易度が理想的だと言われています。簡単すぎると脳が活性化せず、難しすぎるとストレスで学習効率が下がってしまうんです。
これは『ヴィゴツキーの最近接発達領域』という理論に基づいています。『今はまだ難しいけど、少し努力すれば到達できる』というレベルの課題に取り組むことで、最も効果的に能力を伸ばせるというものです。
実際、私の研究でも、教科書の例題を解いた直後に、少し応用的な問題に挑戦した方が、基本問題ばかり繰り返すより理解が深まることが分かってきました。
つまり、勉強で『ちょっと分からない』と感じることは、実は成長のチャンスなんです。ただし、『全く分からない』になってしまっては逆効果です。そんな時は、基礎に戻って少しずつ難易度を上げていくのがおすすめです。
教育実習ホームルーム・朝の会ネタ⑬:好きな本の紹介
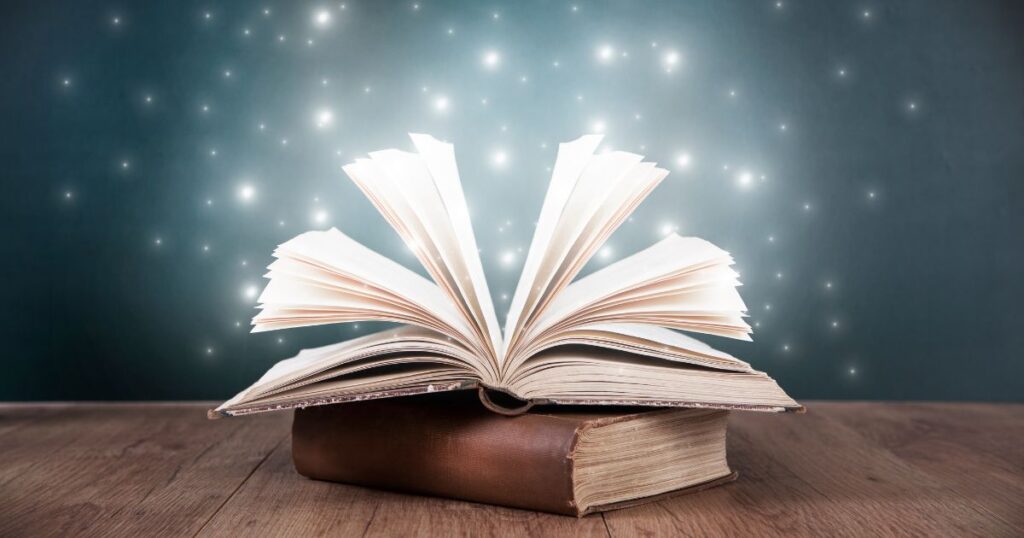
教育実習の朝の会・ホームルームで扱えるネタ13個目は、「好きな本の紹介」です。
「好きな本の紹介」を取り上げるよさとコツ
本の紹介には、
- 読書の楽しさや知識を広げることの素晴らしさ
- 読書への興味
などを伝えられるよさがあります。
本の紹介のときには、以下のポイントを意識するとよいでしょう。
- あらすじの簡潔な説明
- 印象に残った場面や言葉
- 読んで得られた気づき
- 児童生徒たちへのおすすめポイント
また、児童生徒の年齢や興味に適した本を選ぶようにしましょう。
好きな本の紹介の例文
例文(小学生向け)
今日は、私の大好きな本、『かいけつゾロリ』シリーズを紹介します。主人公のゾロリは、いたずら大好きのキツネで、『いたずらの王者になる!』という大きな夢を持っています。イシシとノシシという双子のイノシシの子どもたちと一緒に、次々と大冒険をする物語です。
私が特に好きなのは、ゾロリが失敗しても、絶対にあきらめないところ。例えば、お城に入るための作戦が失敗しても、すぐに次の面白いアイデアを考えて挑戦します。それに、困っている人がいると、強がっているけれど、最後はちゃんと助けてあげる優しい心も持っているんです。
私が初めてゾロリに出会ったのは小学校2年生の時。図書館で見つけて、面白くて一気に読んでしまいました。特に、ゾロリが考える作戦がとてもユニークで、「次はどんな作戦を思いつくんだろう?」とワクワクしながら読みました。
実は今でも新しい巻が出ると読んでいるんですよ。なぜかというと、ゾロリたちが「絶対にあきらめない」姿勢から、いつも元気をもらえるからです。それに、イシシとノシシのように、仲間と協力することの大切さも教えてくれます。
みなさんもぜひ、ゾロリと一緒に冒険の旅に出かけてみてください。きっと、たくさんの笑顔と勇気をもらえると思いますよ。
例文(中学生向け)
今日は私が中学校の頃好きだった本『都会のトム&ソーヤ』を紹介します。
この本は、現代の中学生が主人公の探偵小説です。でも普通の探偵小説とは違って、主人公の内藤くんは『ふつうの中学生』。特別な能力があるわけでもないのに、身の回りで起こる不思議な出来事を、友達と一緒に解決していきます。
私が特に好きなのは、主人公たちが『頭を使って』謎を解いていくところ。スマートフォンやパソコンだけに頼るのではなく、図書館で調べものをしたり、実際に現場を調査したりと、地道な努力で真実に近づいていくんです。
中学1年生の時に読み始めて、次の巻が出るのをいつも楽しみにしていました。学校での友情や、家族との関係など、私たちの日常にもある出来事が上手く織り込まれているんです。
探偵小説が好きな人はもちろん、学校生活を舞台にした物語が好きな人にもおすすめの本です。興味のある人は読んでみてくださいね。
例文(高校生向け)
今日は、私が高校生の時にハマった小説『コーヒーが冷めないうちに』を紹介します。
この小説は、不思議な喫茶店が舞台です。その店では、ある席に座ると『過去に戻れる』という設定なのですが、ただし「コーヒーが冷めないうちに」現在に戻ってこないといけません。また、過去を変えることはできないというルールもあります。
一見ファンタジーのような設定ですが、実は人間の『心』を深く描いた作品です。登場人物たちは皆、何かを後悔していたり、言い出せなかった想いを抱えていたりします。彼らは過去に戻っても状況を変えることはできないのに、なぜ戻りたいと願うのか。
私がこの本に出会ったのは高校2年生の時。受験勉強に追われる日々で、『もし違う選択をしていたら』と考えることもありました。でも、この本は『過去は変えられなくても、それを受け入れて前に進むことができる』ということを教えてくれました。
特に印象的なのは、『大切なのは過去を変えることではなく、過去と向き合うこと』というメッセージです。高校生の皆さんなら、きっと共感できる部分が多いはずです。興味のある人は読んでみてくださいね。
教育実習ホームルーム・朝の会ネタ⑭:今日は何の日?

教育実習の朝の会・ホームルームで扱えるネタ14個目は、「今日は何の日?」です。
「今日は何の日?」を取り上げるよさとコツ
その日にまつわる歴史的出来事や記念日を紹介することで、生徒たちの知識を広げ、時事問題への関心を高めることができます。
ネットで「今日は何の日?」と調べたら、色んな情報を手に入れられるので、子どもたちの興味にあったものを選んで話をしてみるといいですね。
今日は何の日?の例文
みなさん、今日1月9日は『風邪の日』なんです。
昔の日本では、この時期になると風邪が流行っていたそうです。そこで、みんなで風邪予防について考える日として『風邪の日』が作られました。
私が小さい頃、お母さんに教えてもらった風邪予防の3つの魔法があります。
「うがいの魔法」:学校から帰ったらすぐにうがい
「手洗いの魔法」:石けんで泡を作ってしっかり洗う
「ぐっすりの魔法」:早寝早起きで十分な睡眠
今の季節は特に風邪をひきやすいので、みなさんもこの3つの魔法を使って、元気に過ごしましょうね。
みなさん、今日は何の日か知っていますか?そう。1月10日は『110番の日』です。
110番は、警察に助けを求める大切な電話番号です。でも、気をつけてほしいことがあります。それは、本当に困った時、危険な時だけに使うようにしましょう。
どんなときにかけていいかというと、
・交通事故を見かけた時
・不審者を見かけた時
・誰かが怪我をしている時
などです。
先日、私は大学の近くで自転車の事故を目撃しました。すぐに110番に電話をして、『○○交差点で自転車と車が接触しました』『怪我人が1名います』と伝えました。場所と状況を落ち着いて伝えることが大切なんです。
みなさんも、110番は『命を守る大切な番号』ということを覚えておいてくださいね。
教育実習ホームルーム・朝の会ネタ⑮:特技を披露する

教育実習の朝の会・ホームルームで扱えるネタ15個目は、「特技を披露する」です。
自身の特技を披露することには、
- 児童生徒たちとの距離を縮められる
- 授業の雰囲気を和らげる
- 子どもたちに尊敬のまなざしで見てもらえる
などのよさがあります。
披露する特技は、教室でも安全にできるものにしましょう。
例えば、以下のような特技があれば披露してみるのもいいかもしれませんね。
- けん玉
- お手玉・ジャグリング
- 手品
- 書道
- 折り紙
- 切り絵
- ボイスパーカッション
- ギター
- ピアノ
- 歌
この他にも、教室でできそうな特技があったら披露してみるといいですね。
まとめ:教育実習のホームルーム・朝の会ネタはいくつか準備しておこう

教育実習でのホームルーム・朝の会のネタについて紹介してきました。
まとめると、
- 朝の会・ホームルームで扱えるネタ
- 偉人の話
- 名言・座右の銘の紹介
- 学生時代の話
- 学生時代の友達との今の関係
- 大学生の一日
- 名前の話
- 勉強のやり方に役立つ話
- 世界の面白い文化
- 今年の目標と進捗状況
- 健康ワンポイントアドバイス
- 自分の専門教科を活かした雑学
- 好きな本の紹介
- 今日は何の日?
- 特技を披露する
これらのネタを、児童生徒の興味に合わせて話すとよいでしょう。
教育実習中は、何度か朝の会・ホームルームで話をすることがあるかと思います。
15選のうちからいろいろ選びながら、児童生徒との良好な関係づくりにつなげてくださいね。
教育実習「ノウハウカテゴリ」には、以下の記事があります。
気になる記事をタップで読んでみよう↓
\まとめ記事はこちら/
個別記事