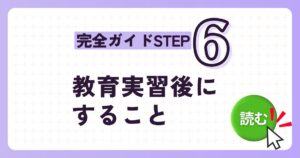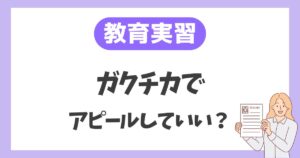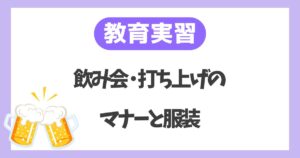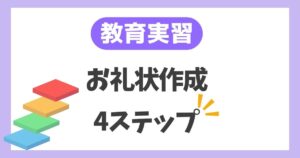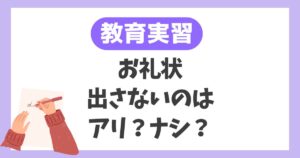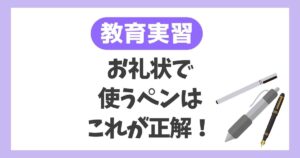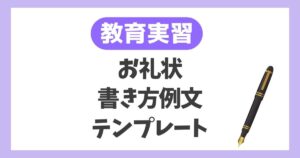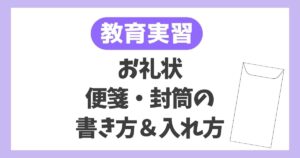教育実習の感想・レポート・学んだことの書き方まとめ|例文も紹介
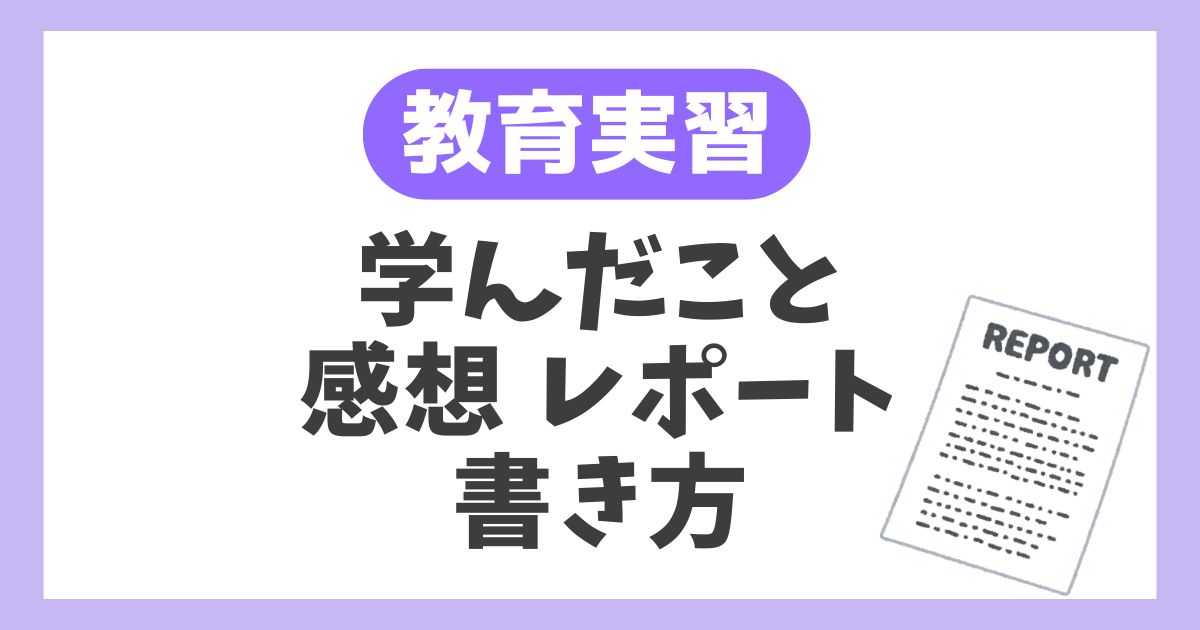
「教育実習の感想文・レポートってどうまとめればいいんだろう…」
「書き方がわからない…」
と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
教育実習が終わったのもつかの間、大学に戻ったら「教育実習の感想」「教育実習で学んだこと」などのレポート提出が待っていますね。
この記事では、教育実習レポートの基本的な書き方と、校種別の具体的な例文を紹介します。
- 教育実習のレポート書き方(2パターン)
- 小学校教育実習のレポート例文
- 中学校教育実習のレポート例文
- 高等学校教育実習のレポート例文
記事を読むことで、教育実習レポートの書き方がわかり、効率よくレポート提出できるようになりますよ。
教育実習の「感想」「学んだこと」レポートの書き方まとめ

教育実習の感想・学んだことレポートには、大きく分けて2通りの書き方があります。
- 時系列で書く方法
- トピックごとに書く方法
大学で特に形式が指定されていない場合は、自分の書きやすい書き方を選びましょう。
それぞれの書き方を紹介しますね。
時系列で書く
教育実習レポートの書き方1つ目は「時系列で書く」方法です。
教育実習での出来事・学んだこと・感じたことを、時系列で書いていきます。
実習日誌を見たり、カレンダーを振り返ったりしながら書いていけばよいので、書き手としては書きやすい方法であるといえます。
同時に、実習での成長過程も伝わりやすい書き方となっています。
具体的には、以下のような構成で書きます。
- 教育実習の概要と目標
- 初日の様子
- 1週目の取り組み
- 2週目の取り組み
- 3週目の取り組み・査定授業について
- 最終日の様子
- 学んだこと・感想
具体的な書き方は、記事後半の書き方例文をご覧ください。
トピックに分けて書く
教育実習レポートの書き方2つ目は「トピックに分けて書く」方法です。
トピックごとに分けて書く場合は、学んだことを体系的にまとめることができます。
「児童生徒との関わり」「授業」など、学びをまとめて書くので、あとで振り返った時にわかりやすい書き方といえます。
また、読み手にも教育実習での成果がわかりやすいです。
具体的には、以下のような構成で書きます。
- はじめに(概要と目標)
- 児童生徒との関わりについて
- 授業見学で学んだこと
- 授業実践で学んだこと
- まとめ(総括・感想・今後の活用)
2〜4の部分は、自分が決めたトピックに変更して書いてOK。
(例えば、「指導案作成で学んだこと」「生徒指導で学んだこと」などに変更してよいということ)
具体的な書き方は、記事後半の書き方例文をご覧ください。
大切なのは「あなたにしか書けないエピソード」
レポートを書くときに大切なことは「あなたにしか書けないエピソードを入れ込む」ということ。
抽象的なことばかりが書かれたものに、教育実習レポートの価値はありません。
「あなたにしか書けないエピソードを入れ込む」ために、以下の3つの要素は必ずいれるようにしましょう。
- 教育実習の目標に対する成果
- 児童生徒との具体的なエピソード
(会話文などが入るとよりよいですね) - 失敗から何を学び、どう改善したのか、というエピソード
この3つのエピソードをいれることで、抽象的な感想だけでなく、世界に1つしかないあなただけの教育実習レポートが出来上がります。
【小学校】教育実習の感想・レポート・学んだことの書き方例文

ここからは、「時系列で書く」「トピックに分けて書く」の2つの書き方を使った、具体的なレポートの例文を紹介します。
まずは、小学校の教育実習レポートの例から見ていきましょう。
例文1(時系列で書く)
①教育実習の概要と目標
私は○○大学附属小学校で4週間の教育実習を行いました。担当は3年2組で、算数2回(かけ算の筆算)、国語1回(物語文の読解)、道徳1回(友情)の計4回の授業を担当させていただきました。実習の目標として、「児童一人一人の考えを大切にし、互いに学び合える授業づくり」を掲げました。これは、小学校という発達段階において、自分の考えを表現する力と、他者の考えから学ぶ力を育むことが重要だと考えたためです。
②初日の様子
初日、附属小学校の門をくぐった時、身の引き締まる思いでした。朝の職員室では、実習生としての心構えについて校長先生からお話をいただき、教育者としての責任の重さを実感しました。担当の3年2組の教室に入ると、32名の児童たちが好奇心いっぱいの表情で迎えてくれました。自己紹介では、「みなさんと一緒に学び合える先生になりたいです」と伝えました。
③1週目の取り組みと感想・学んだこと
1週目は授業観察と児童理解に努めました。担任の先生の授業では、発問一つひとつに意図があり、児童の反応を予想した展開に感銘を受けました。休み時間には積極的に教室に残り、児童たちと給食も一緒に食べることで、一人一人の個性や人間関係について理解を深めることができました。特に印象に残っているのは、算数が苦手だという男子児童との会話です。「間違えるのが怖い」という言葉を聞き、間違いを恐れずに挑戦できる授業づくりの重要性を認識しました。
④2週目の取り組みと感想・学んだこと
2週目には国語の授業を担当しました。物語文「モチモチの木」の読解では、登場人物の気持ちの変化を考える授業を計画しました。しかし、教師の発問が曖昧で、児童たちの考えを十分に引き出せませんでした。また、板書が整理されておらず、話し合いの流れが見えにくくなってしまいました。指導教官からは「発問を具体的にすること」「児童の意見を板書に効果的に位置付けること」という指導をいただきました。
⑤3週目の取り組みと感想・学んだこと
3週目には道徳と1回目の算数の授業を行いました。道徳では友情をテーマに、グループでの話し合い活動を取り入れましたが、時間配分に課題が残りました。算数では、かけ算の筆算の導入でしたが、既習事項の確認が不十分で、つまずく児童が多く出てしまいました。これらの反省を踏まえ、査定授業に向けて準備を進めました。
⑥3週目後半から4週目の取り組みと感想・学んだこと(主に査定授業について)
査定授業は、2回目の算数「2桁×1桁のかけ算の筆算」を担当しました。これまでの反省を活かし、以下の3点に特に注意を払いました。1つ目は、既習事項の丁寧な確認です。位取り表を用いて十の位と一の位の計算の違いを明確にしました。2つ目は、児童が自分の考えを発表しやすい雰囲気づくりです。「間違えても大丈夫、みんなで考えよう」と声をかけ続けました。3つ目は、板書の構造化です。児童の多様な考え方を位取り表と関連付けて示すことで、理解を深められるよう工夫しました。その結果、「わかった!」「楽しかった!」という声が多く聞かれ、特に算数が苦手だった児童が自信を持って発表する場面が見られました。
⑦最終日の様子
最終日、児童たちから一人一人手作りのメッセージカードをもらいました。「算数の授業が分かりやすかった」「また一緒に勉強したい」という言葉に、涙が出そうになりました。4週間という短い期間でしたが、児童たちと共に成長できた実感がありました。
⑧全体を通した感想
4週間の実習を通して、「児童一人一人の考えを大切にする」という目標に向けて、少しずつ成長できたと感じています。特に、つまずきや間違いを学びの機会として捉え、クラス全体で共有することの大切さを学びました。また、教科の特性に応じた指導法の工夫も、実践を通して学ぶことができました。算数では筆算の仕方を視覚的に示す工夫、国語では場面の読み深めを促す発問の工夫、道徳では自己の生き方について考えを深める場の設定など、教科の特質に応じた指導の在り方について多くの示唆を得ることができました。この貴重な経験を糧に、今後も教員としての資質向上に努めていきたいと思います。
例文2(トピックに分けて書く)
①はじめに(概要と目標)
私は○○大学附属小学校で4週間の教育実習を行いました。担当は6年1組で、理科2回(「水溶液の性質」)、算数1回(「円の面積」)、道徳1回(「思いやりの心」)の計4回の授業を担当させていただきました。実習の目標として、「科学的な探究心を育み、対話を通じて学びを深める授業づくり」を掲げました。これは、理科を主担当とする中で、実験や観察を通じた気づきを、クラス全体の学びへと発展させたいと考えたためです。
②児童生徒との関わりについて
児童との関わりで最も印象に残っているのは、理科の実験に苦手意識を持つ女子児童とのエピソードです。休み時間に「薬品を扱うのが怖い」と不安を打ち明けられ、実験の安全な取り扱い方を丁寧に説明したり、実験準備を一緒に行ったりする時間を設けました。また、給食の時間には各班を回って会話を交わし、児童一人一人の興味・関心や性格について理解を深めることができました。教科指導以外の場面でも、朝の会や帰りの会での児童との対話を大切にし、信頼関係の構築に努めました。
③授業見学で学んだこと
担任の先生の授業見学では、発達段階に応じた指導の工夫に多くの気づきがありました。例えば理科の授業では、実験の前に必ず児童に予想を立てさせ、その根拠を説明させることで、科学的思考力を育んでいました。また、児童の素朴な疑問を クラス全体の学習課題へと発展させる手法は、特に印象的でした。他教科の授業見学でも、教科の特性に応じた指導法や、児童の主体的な学びを引き出す工夫など、多くの示唆を得ることができました。
④授業実践で学んだこと
最初の理科の授業では、リトマス紙を使った水溶液の性質の学習を行いました。しかし、実験手順の説明が不十分だったため、各班で混乱が生じました。また、結果の考察において、児童の気づきを十分に引き出せないまま、教師主導の説明に終始してしまいました。指導教官からは「実験の目的を明確にすること」「児童の気づきを大切にした展開を心がけること」という指導をいただきました。
この反省を活かし、査定授業(理科2回目)では、より丁寧な授業設計を心がけました。「水溶液の仲間分け」という単元で、実験の目的と手順を視覚的に示したワークシートを用意し、安全面への配慮も徹底しました。また、各班の実験結果を黒板に整理して掲示し、気づいたことを発表し合う時間を十分に確保しました。特に、予想と結果が異なった班の発表を取り上げ、なぜそうなったのかをクラス全体で考察する場面を設けました。その結果、「実験が楽しかった」「友達の考えが参考になった」という感想が多く聞かれ、主体的な学びの実現につながりました。
⑤まとめ(総括・感想・今後の活用)
4週間の実習を通じて、「科学的な探究心を育む」という目標に向けて、確かな手応えを感じることができました。特に、教師主導の展開に終始した最初の授業から、児童の気づきを大切にした対話的な学びを実現できた査定授業への成長は、大きな学びとなりました。また、休み時間や給食時間での関わりを通じて、児童理解の深化が授業改善につながることも実感しました。
今後は、この経験を活かし、以下の3点を意識した授業づくりを心がけていきたいと思います。1つ目は、児童の素朴な疑問や気づきを大切にし、それを学びの出発点とすること。2つ目は、実験や観察の場面で、安全面への配慮と主体的な探究活動のバランスを取ること。3つ目は、個々の児童の特性を理解し、それぞれの学び方に応じた支援を行うことです。附属小学校での実習という貴重な経験を糧に、さらなる成長を目指して努力を続けていきたいと思います。
【中学校】教育実習の感想・レポート・学んだことの書き方例文

続いて、中学校の教育実習レポートの例を見ていきましょう。
例文1(時系列で書く)
①教育実習の概要と目標
私は母校である○○中学校で3週間の教育実習を行いました。担当は理科で、1年生の「光の性質」の単元を4回担当させていただきました。実習の目標として、「生徒一人一人と真摯に向き合い、全員が主体的に参加できる授業づくり」を掲げました。これは、私自身の中学時代の経験から、教科への興味や理解度には個人差があり、それぞれの生徒に応じた支援が重要だと考えたためです。
②初日の様子
初日、職員室に入った時の緊張は今でも鮮明に覚えています。13年前に生徒として過ごした学校に、今度は教員として立つことへの感慨深さと責任の重さを感じました。担当の1年2組の生徒たちは、期待と好奇心に満ちた眼差しで私を見つめていました。自己紹介では、「私も皆さんと同じようにこの教室で授業を受けていた一人です」と話すと、生徒たちは目を輝かせて聞いてくれました。
③1週目の取り組みと感想・学んだこと
1週目は主に授業見学と生徒観察を行いました。休み時間には積極的に教室に足を運び、生徒たちと交流を持つよう心がけました。特に印象に残っているのは、理科が苦手だという女子生徒との会話です。「実験は好きだけど、理論がわからない」という悩みを聞き、これを授業づくりの重要な視点として取り入れることにしました。また、ベテランの先生方の授業を見学させていただき、発問の仕方や板書の構成、生徒の反応の引き出し方など、多くのことを学ばせていただきました。
④2週目の取り組みと感想・学んだこと
2週目から実際の授業を担当しました。最初の授業では、光の反射の法則を扱いました。しかし、理論的な説明に時間をかけすぎてしまい、実験の時間が不足。また、板書計画が不十分で、生徒たちがノートを取る時間も確保できませんでした。指導教官からは「生徒の活動時間を十分に確保すること」「板書計画をしっかり立てること」という指導を受けました。特に反省したのは、教師の説明が長くなりすぎて、生徒たちの集中力が途切れてしまった点です。授業後、ある生徒が「先生、もっと実験の時間が欲しかった」と正直に話してくれたことが、大きな学びとなりました。
⑤3週目の取り組みと感想・学んだこと
この反省を活かし、査定授業では「凸レンズによる像の結び方」について、実験を中心に据えた授業を計画しました。実験手順を図解付きでプリントに示し、グループワークの時間を十分に確保。さらに、机間指導の際には、特に理論の理解に不安を持つ生徒に重点的な支援を行いました。板書も「導入→実験→考察→まとめ」という流れを明確にし、生徒がノートを取りやすいよう工夫しました。その結果、全てのグループが実験を完遂し、多くの生徒が「像の結び方が理解できた」「実験と理論がつながった」と感想を述べてくれました。特に嬉しかったのは、1週目に悩みを打ち明けてくれた生徒が「今日の授業、わかりやすかったです!」と笑顔で言ってくれたことです。
⑥最終日の様子
最終日、生徒たちから手作りの寄せ書きをもらいました。「実験が楽しかった」「理科が少し好きになりました」「失敗してもあきらめない先生の姿が印象的でした」という言葉に、胸が熱くなりました。生徒たちとの別れは寂しいものでしたが、この3週間で得た絆は私の宝物となりました。
⑦全体を通した感想
3週間の実習を通じて、「わかる」と「できる」をつなぐ授業づくりの重要性を学びました。当初の目標であった「生徒一人一人と向き合う」ことについては、休み時間の交流や机間指導を通じて、ある程度達成できたと感じています。また、「全員が主体的に参加できる授業」については、失敗と改善を重ねることで、最終的に手応えのある授業を行うことができました。特に、実験と理論をバランスよく組み合わせることの重要性を、身をもって学びました。また、生徒の声に耳を傾け、それを授業改善に活かすことの大切さも実感しました。この経験を糧に、今後も教員としての資質向上に努めていきたいと思います。
例文2(トピックに分けて書く)
①はじめに(概要と目標)
私は母校である○○中学校で3週間の教育実習を行いました。担当は2年生の数学で、「連立方程式」の単元を4回担当させていただきました。実習の目標として、「生徒の思考過程を大切にし、数学的な見方・考え方を育む授業づくり」を掲げました。これは、数学が苦手な生徒にとっても、考えることの楽しさや解決できた時の喜びを感じられる授業を目指したいと考えたためです。
②児童生徒との関わりについて
生徒との関わりで最も印象に残っているのは、数学が苦手だという男子生徒とのエピソードです。休み時間に教室で自主学習をしている彼に声をかけると、「答えは出せても、なぜそうなるのかわからない」と悩みを打ち明けてくれました。その日から放課後に質問時間を設け、一緒に解き方の意味を考える時間を持ちました。また、給食の時間には積極的に教室に足を運び、生徒たちと様々な会話を交わしました。部活動見学では、数学の授業では見られない生徒たちの生き生きとした表情に触れ、教科指導以外での関わりの重要性を実感しました。
③授業見学で学んだこと
指導教官の授業見学では、特に発問の工夫と板書構成に多くの学びがありました。例えば、連立方程式の単元では、「なぜ2つの式が必要なのか」という本質的な問いから入り、生徒の興味を引き出していました。また、生徒の誤答を効果的に活用し、クラス全体で考えを深める場面では、教科指導の奥深さを感じました。他教科の授業見学でも、教科の特性に応じた指導法や、生徒の反応の引き出し方など、多くの示唆を得ることができました。
④授業実践で学んだこと
最初の授業では、加減法による連立方程式の解き方を扱いました。しかし、解法の手順を説明することに重点を置きすぎ、「なぜこの手順で解けるのか」という理解を深める機会を十分に設けることができませんでした。また、生徒の理解度を確認しないまま先に進んでしまい、後半では多くの生徒が混乱する場面がありました。指導教官からは「生徒の思考過程を大切にすること」「理解度の確認を適切に行うこと」という指導をいただきました。
この反省を活かし、査定授業では「連立方程式の利用」において、日常生活の問題を教材として扱いました。問題場面を理解する時間を十分に設け、「何がわかっていて、何を求めればよいのか」をクラス全体で確認しました。また、グループ活動を取り入れ、式の立て方について話し合う機会を設けました。机間指導では、特につまずきが見られる生徒に対して、図や表を用いた思考の手助けを行いました。その結果、「式の意味がわかった」「友達の考え方が参考になった」という感想が多く聞かれ、生徒主体の学びを実現することができました。
⑤まとめ(総括・感想・今後の活用)
3週間の実習を通じて、「生徒の思考過程を大切にする」という目標に向けて、着実な成長を感じることができました。特に、解法の手順を教えることに重点を置いた最初の授業から、生徒の思考を促し、対話を通じて理解を深める査定授業への転換は、大きな学びとなりました。また、休み時間や放課後の関わりを通じて、生徒一人一人の特性や学習に対する思いを理解することの重要性も実感しました。
今後は、この経験を活かし、以下の3点を意識した授業づくりを心がけていきたいと思います。1つ目は、生徒の思考過程を可視化し、クラス全体で共有する機会を設けること。2つ目は、生徒の誤答や躓きを学びの機会として積極的に活用すること。3つ目は、教科指導以外での関わりを通じて得た生徒理解を、授業改善に活かしていくことです。教育実習で得たこれらの学びを糧に、さらなる成長を目指して努力を続けていきたいと思います。
【高校】教育実習の感想・レポート・学んだことの書き方例文

最後に、高校の教育実習レポートの例を見ていきましょう。
例文1(時系列で書く)
①教育実習の概要と目標
私は母校である○○高等学校で3週間の教育実習を行いました。担当は高校1年生の古文で、「伊勢物語」の「筒井筒」を4回担当させていただきました。実習の目標として、「古典に対する興味・関心を引き出し、主体的に作品の理解を深められる授業づくり」を掲げました。これは、私自身の高校時代、古文の授業で作品の背景や心情に触れることの面白さを知り、古典への関心を深めた経験に基づいています。
②初日の様子
初日、6年ぶりに母校の玄関を潜り、懐かしい校舎に胸が高鳴りました。職員室では、恩師の先生方が温かく迎えてくださり、生徒として過ごした日々が昨日のことのように感じられました。担当の1年A組に入ると、かつての自分と重なる生徒たちの姿に、教壇に立つ責任の重さを実感しました。
③1週目の取り組みと感想・学んだこと
1週目は主に授業見学と生徒理解に努めました。放課後には母校のバドミントン部の練習も見学させていただき、6年前に自分が汗を流した思い出の体育館で、現役部員たちの熱心な練習に感動しました。授業では、指導教官の古文の授業を拝見し、文法指導と作品理解をバランスよく組み合わせる手法や、現代の生徒の視点に立った作品解釈の示し方など、多くのことを学ばせていただきました。
④2週目の取り組みと感想・学んだこと
2週目から実際の授業を担当しました。最初の授業では「筒井筒」の導入部を扱いましたが、文法解説に時間をかけすぎて、物語の面白さを十分に伝えられませんでした。また、生徒の反応を見ながら授業を進めるという基本的なスキルが不足していたため、教室全体が受け身の雰囲気となってしまいました。指導教官からは「文法事項は要点を絞ること」「生徒との対話を大切にすること」という指導をいただきました。
⑤3週目の取り組みと感想・学んだこと
この反省を活かし、査定授業では「筒井筒」の後半部分、特に主人公の妻の心情が印象的に描かれる場面を扱いました。事前に重要な文法事項をプリントにまとめ、授業では登場人物の心情理解に重点を置きました。また、グループワークを取り入れ、「もし自分が主人公の妻の立場だったら」という視点で意見を交換する時間を設けました。その結果、「古文でも登場人物の気持ちに共感できた」「今の時代にも通じる話だと思った」といった感想が聞かれ、生徒たちの活発な発言を引き出すことができました。
⑥最終日の様子
最終日、生徒たちから心のこもった寄せ書きをもらいました。「古文が少し好きになりました」「先生の授業は分かりやすかった」という言葉に加え、「部活でアドバイスをくれてありがとう」というメッセージもあり、教科指導以外でも生徒たちと絆を築けたことを実感しました。
⑦全体を通した感想
3週間の実習を通じて、古典教育の難しさと可能性を学びました。当初の目標であった「古典への興味・関心を引き出す」ことについては、生徒たちの反応から、ある程度達成できたと感じています。特に、文法指導に重点を置きすぎた最初の授業から、作品の本質的な理解や現代的な解釈に焦点を当てた査定授業への転換は、大きな成長だったと思います。また、バドミントン部の指導を通じて、教科指導以外での生徒との関わりの重要性も実感しました。部活動では、生徒の新たな一面を発見し、それを授業での生徒理解にも活かすことができました。母校での実習という特別な経験を通じて、教員という職業の魅力と責任を改めて認識し、今後の教員生活への意欲を一層高めることができました。この経験を糧に、生徒一人一人の成長を支える教員を目指して努力を続けていきたいと思います。
例文2(トピックに分けて書く)
①はじめに(概要と目標)
私は母校である○○高等学校で3週間の教育実習を行いました。担当は高校2年生の世界史で、「産業革命とその影響」の単元を4回担当させていただきました。実習の目標として、「歴史的事象の因果関係を多角的に考察し、現代との繋がりを見出せる授業づくり」を掲げました。これは、単なる暗記に終始せず、歴史を通じて現代社会を理解する視点を育みたいと考えたためです。
②児童生徒との関わりについて
生徒との関わりで印象深かったのは、世界史に苦手意識を持つ生徒との対話です。休み時間に「年号や出来事を覚えるのが大変」と相談を受け、歴史的事象のつながりを図式化して理解する方法を一緒に考えました。また、放課後には吹奏楽部の練習を見学させていただき、授業では見られない生徒たちの表情や、音楽を通じた表現力の豊かさに感銘を受けました。部活動見学を通じて、教科の枠を超えた生徒理解の重要性を実感しました。さらに、給食指導や清掃指導などの場面でも、積極的に生徒と関わり、信頼関係の構築に努めました。
③授業見学で学んだこと
指導教官の授業見学では、特に教材活用の工夫と発問の仕方に多くの学びがありました。例えば、産業革命の授業では、当時の工場労働者の生活を示す史料や写真を効果的に用い、生徒の興味関心を引き出していました。また、「なぜ産業革命がイギリスで起こったのか」という本質的な問いから授業を展開する手法は、歴史的思考力を育む上で非常に参考になりました。他教科の授業見学でも、教科の特性に応じた指導法や、生徒の主体的な学びを促す工夫など、多くの示唆を得ることができました。
④授業実践で学んだこと
最初の授業では、産業革命の技術的側面を扱いましたが、事実の説明に終始してしまい、生徒の思考を促す機会を十分に設けることができませんでした。また、パワーポイントの使用に気を取られ、生徒の反応を見ながら授業を進めるという基本的なスキルが不足していました。指導教官からは「史実の背景にある社会構造の変化に注目させること」「視聴覚教材は補助的に用いること」という指導をいただきました。
この反省を活かし、査定授業では「産業革命が社会にもたらした影響」をテーマに、より生徒の思考を重視した展開を心がけました。具体的には、当時の労働者の証言や工場法の条文などの史料を読み解く活動を取り入れ、グループでの討論時間を設けました。また、現代の働き方改革との比較を通じて、歴史的課題の現代的意義について考察する機会も設定しました。その結果、「歴史が現代につながっていることがわかった」「様々な立場から考えることができた」という感想が聞かれ、歴史への興味関心を高めることができました。
⑤まとめ(総括・感想・今後の活用)
3週間の実習を通じて、「歴史的事象の多角的な考察」という目標に向けて、着実な成長を感じることができました。特に、事実説明に偏重した最初の授業から、史料の活用と討論を通じて歴史的思考力を促す査定授業への発展は、大きな学びとなりました。また、部活動見学や日常的な関わりを通じて、生徒理解の深化が授業改善につながることも実感しました。
今後は、この経験を活かし、以下の3点を意識した授業づくりを心がけていきたいと思います。1つ目は、適切な史料の選択と活用を通じて、生徒の思考を促すこと。2つ目は、現代的な課題との関連付けを通じて、歴史学習の意義を実感させること。3つ目は、生徒一人一人の興味関心や学習スタイルに応じた支援を行うことです。母校での教育実習という貴重な経験を糧に、さらなる成長を目指して努力を続けていきたいと思います。
まとめ:教育実習の「感想・学んだこと」レポートは、あなたにしか書けないエピソードを入れて書こう
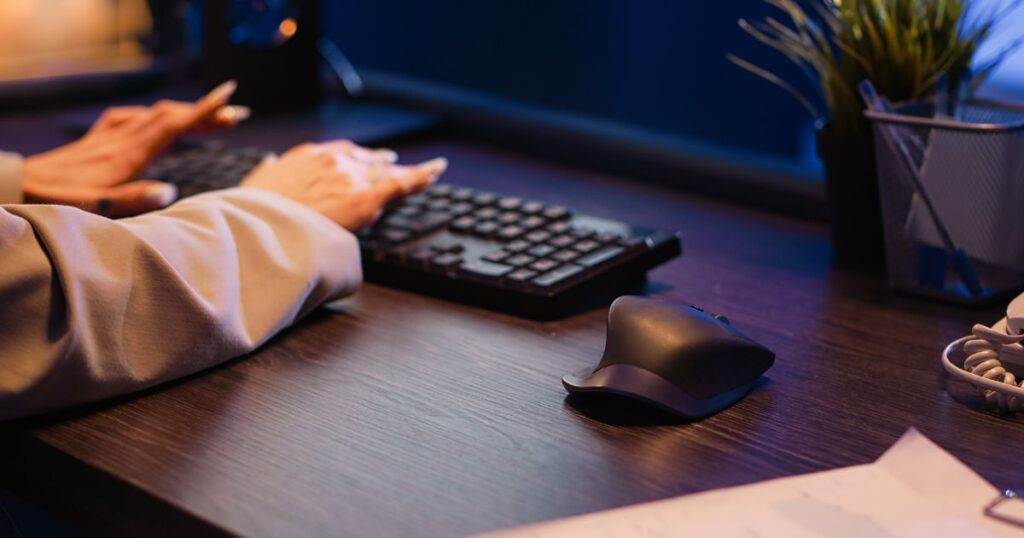
教育実習のレポート作成について紹介してきました。
まとめると、
- 時系列で書く方法
- 実習の目標設定から最終日までを順に振り返る
- 日々の成長過程が伝わりやすい
- 実習日誌を参考に書きやすい
- トピックごとに書く方法
- 児童生徒との関わり、授業見学、授業実践など項目別
- 学びを体系的にまとめられる
- 読み手に成果が伝わりやすい
- レポートに必ず含めるべき要素
- 実習の目標に対する具体的な成果
- 児童生徒との具体的なエピソード
- 失敗から学んだことと改善点
レポートは単なる感想文ではなく、実習での学びと成長を体系的にまとめます。
そして、特に重要なのは、あなたにしか書けないエピソードを盛り込むこと。
失敗や成功、児童生徒との心に残る出来事など、具体的なエピソードを通して、あなたの成長を書き表していきましょう。